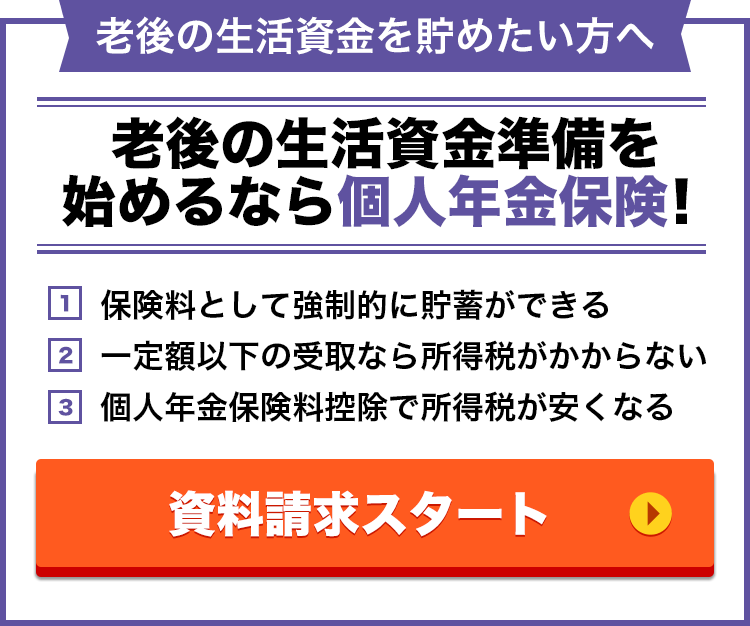個人年金保険のメリットの一つに個人年金保険料控除があります。他の保険とは別枠で保険料控除が受けられるので無駄になりにくいです。個人年金保険料控除でどれくらいの所得税・住民税を節税できるのでしょうか?
目次
どんな保険が必要か、いくらの保障が必要なのか分からない方へ
簡単な質問に答えるだけで、あなたに必要な備えと保障金額がすぐにわかります。
最短1分、無料でご利用可能ですので、ぜひお試しください!
\自分に必要な保障がわかる!/
個人年金保険料控除とは?
個人年金保険料控除とは、一定の条件を満たした個人年金保険の保険料を支払うと、1年間に支払った保険料総額に応じて所得控除を受けられ、所得税・住民税が安くなる制度です。
個人年金保険料控除は生命保険料控除の一種で、生命保険料控除は他に、一般生命保険料控除と介護医療保険料控除があります。個人年金保険は他の保険とは別で枠が用意されているので、終身保険や学資保険などの他の保険で枠が埋まってしまっているということが起きないというメリットがあります。
個人年金保険料控除でいくら節税できる?
個人年金保険料控除でいくら節税できるかは、その人の年間の保険料支払額や所得によって変わります。保険料支払額によって所得控除の金額が変わり、所得によって所得税の税率が変わるためです。
いくらの所得控除を受けられる?
まずは個人年金保険料控除でいくらの所得控除を受けることができるのかです。年間の払込保険料額に応じた個人年金保険料控除の金額は以下の通りです。
| 所得税 | 住民税 | ||
|---|---|---|---|
| 年間払込保険料額 | 控除金額 | 年間払込保険料額 | 控除金額 |
| 2万円以下 | 全額 | 1万2千円以下 | 全額 |
| 2万円超~4万円以下 | (払込保険料×1/2)+1万円 | 1万2千円超~3万2千円以下 | (払込保険料×1/2)+6千円 |
| 4万円超~8万円以下 | (払込保険料×1/4)+2万円 | 3万2千円超~5万6千円以下 | (払込保険料×1/4)+1万4千円 |
| 8万円超 | 一律4万円 | 5万6千円超 | 一律2万8千円 |
※2012年1月1日以降の契約分
例えば、保険料として月5,000円、つまり年6万円支払ったという場合、所得税では6万円×1/4+2万円=3万5000円の控除を、住民税では2万8000円の控除を受けることができます。また、月1万円で年間12万円支払ったという場合では、所得税で4万円、住民税で2万8000円の控除を受けることができます。
いくらの節税ができる?
上で説明した控除額がそのまま節税できる金額というわけではありません。個人年金保険料控除は所得税額や住民税額を計算するための所得を減らすものなので、実際に安くなる金額は控除額に税率をかけた金額です。住民税の税率は地域によって微妙に差異がありますが、全国的にほぼ10%となります。所得税の税率は課税所得によって異なります。所得税額の速算表は以下の通りです。
| 課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超 1800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1800万円超 4000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
※平成27年分以降の税率
参考:国税庁
計算に使うのは課税所得なので、年収そのままの額ではなく、そこから基礎控除や給与所得控除、社会保険料控除といった控除などを行った後の金額です。40歳未満・配偶者なしの給与所得者での目安としては、年収が約440万円以下で税率5%、年収が約640万円以下で税率10%、年収が約1070万円以下で税率20%、年収が約1280万円以下で税率23%となります。
以上から個人年金保険料控除によって、所得税・住民税がどれだけ安くなるか計算したものが以下の表となります。なお、年間の払込保険料が8万円以上の場合で、住民税の税率は一律で10%としています。
| 課税所得 | 所得税軽減額 | 住民税軽減額 | 合計軽減額 |
|---|---|---|---|
| 195万円以下 | 2,000円 | 2,800円 | 4,800円 |
| 195万円超 330万円以下 | 4,000円 | 2,800円 | 6,800円 |
| 330万円超 695万円以下 | 8,000円 | 2,800円 | 10,800円 |
| 695万円超 900万円以下 | 9,200円 | 2,800円 | 12,000円 |
| 900万円超 1800万円以下 | 13,200円 | 2,800円 | 16,000円 |
| 1800万円超 4000万円以下 | 16,000円 | 2,800円 | 18,800円 |
| 4000万円超 | 18,000円 | 2,800円 | 20,800円 |
※復興特別所得税は計算に含めていません。復興特別所得税の税額は、所得税額の2.1%です。
あまり大きな金額ではありませんが、個人年金保険は長い期間保険料を払い続けるので、合計すると意外と大きな金額となります。
▼一括資料請求で保険会社を比較するワケ
▼一括資料請求で保険会社を比較するワケ
- ネットで簡単に資料請求!時間がない方にピッタリ
- 各社保障が違う商品から自分に合った保険を選べる
- 大切な資料を手元に残せる
個人年金保険料控除の注意点
所得税や住民税を安くすることができる個人年金保険料控除ですが、いくつかの注意点もあります。どのようなことに注意が必要か紹介します。
税制適格特約が必要
個人年金保険料控除を受けるためには個人年金保険に個人年金保険料税制適格特約をつける必要があります。この特約がついていない場合は個人年金保険料控除の枠ではなく一般生命保険料控除の枠となります。一般生命保険料控除だと終身保険などの死亡保険や学資保険などと枠が同じであり、他の保険で上限に達しているということが起きやすいので注意が必要です。
-

-
個人年金保険の税制適格特約とは?
個人年金保険の魅力の一つに個人年金保険料控除がありますが、これを受けるためには「個人年金保険料税制適格特約」をつける必要があります。税制適格特約とはどのようなも ...続きを見る
契約内容の変更に制限がある
個人年金保険料税制適格特約をつけると、個人年金保険料控除の条件から外れるような契約条件の変更ができなくなります。個人年金保険料控除が適用される条件は以下の通りです。
- 年金受取人が契約者またはその配偶者であること
- 年金受取人が被保険者と同一人であること
- 保険料の払込期間が10年以上であること
- 年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降であり、かつ年金の受取期間が10年以上であること
年金受取人を子供に変更したい、10年経っていない時点で保険料の残りを一時払で支払いたいというような、個人年金保険料控除の条件から外れる変更は行えません。また一時払に変えることができないので、保険料を払っている期間が10年未満のうちは払済保険への変更も行えません。
iDeCoの方が節税効果は大きい
老後資金を貯めるためのものとして、最近は個人年金保険以外にもiDeCo(個人型確定拠出年金)が注目されています。そして、個人年金保険料控除による所得控除の額よりもiDeCoによる所得控除の額の方が大きいです。iDeCoの場合、小規模企業共済等掛金控除により掛金が全額所得控除となります。iDeCoの掛金の最低額である月5,000円(年間6万円)でも、所得税・住民税で6万円の所得控除が受けられるので、この時点で個人年金保険料控除よりも節税額が大きくなります。
ただし、節税額のみで選ぶのではなく、原則として60歳までは引き出せない、投資信託などで運用する場合は元本割れするリスクもあるというようなiDeCoのデメリットも確認したうえで選ぶようにしましょう。
-

-
個人年金保険とiDeCo、加入するならどっちがいい?
老後資金をどのように貯めるのかは昔から重要なテーマでしたが、「老後資金2000万円問題」を契機としてより注目を集めるようになりました。個人で老後資金を貯めるのに ...続きを見る
まとめ
個人年金保険のメリットの一つとして個人年金保険料控除で所得税・住民税を安くできることがあります。年間の保険料が8万円超の場合で所得税率・住民税率が10%の場合だと所得税と住民税を合わせて6,800円の節税となります。1年だけだと大したことがない金額だと思うかもしれませんが、解約しない限り少なくとも10年は支払うものなので、合計するとちょっとした金額にはなります。個人年金保険料控除を受けるためには税制適格特約が必要なので、条件や制約を含めて確認しておきましょう。

-
著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。