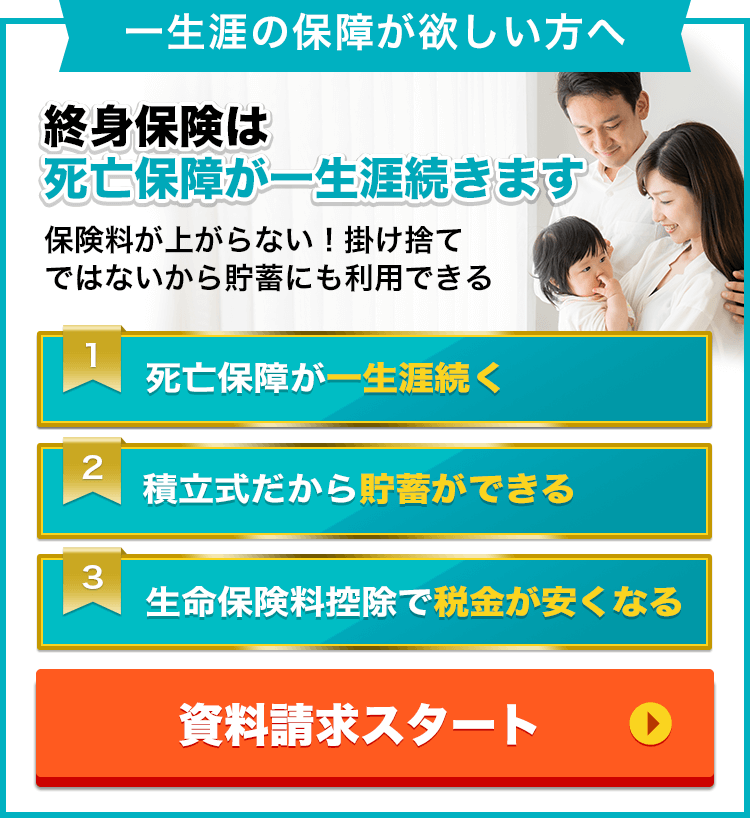結婚や子供が生まれるのを機に生命保険の加入を検討するという方も多いのではないでしょうか。生命保険に加入するうえで決めなければいけないこととして死亡保険金をいくらにするのかということがあります。死亡保険金はいくらに設定するのがよいでしょうか。また、世間の平均はどれくらいなのでしょうか。
どんな保険が必要か、いくらの保障が必要なのか分からない方へ
簡単な質問に答えるだけで、あなたに必要な備えと保障金額がすぐにわかります。
最短1分、無料でご利用可能ですので、ぜひお試しください!
\自分に必要な保障がわかる!/
死亡保険金はいくら必要?
死亡保険金として必要となる金額は、死亡後に遺された家族が必要となる費用から家族が得る収入と貯蓄額を引いた金額です。
貯蓄は各家庭それぞれとして、遺された家族が必要となる金額と遺された家族の収入について解説を加えます。
遺された家族が必要となる金額
遺された家族が必要となる金額としては主に、以下のものが考えられます。
- 葬儀費用
- 家族の生活費
- 住居費
- 子供の教育費
葬儀費用
葬儀費用は日本消費者協会の調査をもとに平均で200万円ほどの金額が紹介されていることが多いです。ただし、葬儀費用は一般葬にするか家族葬にするか、参列人数がどれくらいいるのか、祭壇やお花をどれくらいのものにするのかといったことでも大きく変わります。実際のところでは、規模の大きなお葬式を開かなければ200万円も用意しておけば安心できるというところでしょう。
なお、お墓を新たに用意する場合はその費用も必要となります。どのような墓石を購入するか、お墓の立地などにも左右されますが、150万~300万円ほどとして考えておくとよいでしょう。
家族の生活費
家族の生活費は普段の生活費をベースに月どれくらい必要か考えましょう。1人分の生活費が明確に分かる場合はその分を除きますが、分からないという場合は現在の金額の70~80%を目安として計算される場合が多いです。
そして、この生活費がいつまで必要か考えましょう。配偶者が年金を受け取り始めるまで、末子が独立するまでというようにそれぞれで考えがあると思います。先ほど考えた月額に必要な期間をかけた金額が生活費として用意する必要がある金額です。
住居費
賃貸住宅にお住いの場合は毎月の賃料を生活費に上乗せして考える必要があります。実家に戻るというような場合も引っ越し費用は計算に入れておきましょう。
持ち家で住宅ローンを組んでいて団信を契約しているという場合は、契約者が死亡したら団信によりローンが完済されるので住居費についてはそれほど考えなくてもよいでしょう。ただし、リフォームの必要があるような場合はその費用を計算に入れておきましょう。
子供の教育費
子供の教育費は進路によって大きく異なります。幼稚園から大学まですべて公立の場合だと仕送りを除いて約830万円、すべて私立だと仕送りなしで約2500万円もかかります。幼保無償化など教育費に関する負担は軽減される傾向にありますが、政策がどのような形になるのかは分からないのでそれをあてにするのではなく自分でしっかりと備えておく必要があるでしょう。
参考:文部科学省「子供の学習費調査」(令和5年度)、国立大学等の授業料その他の費用に関する省令、文部科学省「令和5年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金 平均額(定員1人当たり)の調査結果について」
遺された家族の収入
遺された家族の収入としては以下のようなものが考えられます。
- 死亡退職金
- 配偶者の勤労収入
- 遺族年金
死亡退職金
会社によっては従業員が死亡したときに、支払われるはずだった退職金が遺族に支払われることがあります。死亡退職金の制度があるのか、どれくらい受け取れるのかは勤めている会社によって変わりますので各社の就業規則等をご確認ください。なお、500万円×法定相続人の数という非課税限度額を超える死亡退職金は相続税の課税対象となりますのでご注意ください。
配偶者の勤労収入
配偶者が働いている場合はその収入分だけ保険で用意しなければならない金額が減ります。死亡後は働くつもりという場合はすぐに就職先が決まらないことも考慮して計算するようにしましょう。
遺族年金
死亡した方によって生活を支えられていた子供や配偶者は遺族年金を受け取れます。死亡した方が厚生年金に加入していた場合は遺族基礎年金と遺族厚生年金、国民年金のみに加入していた場合は遺族基礎年金の対象となります。
ただし、無条件で受け取れるわけではなく、死亡した方と受け取る方双方に条件があります。遺族基礎年金の対象となるのは生計を維持されていた子供と子のある配偶者で、遺族厚生年金の対象となるのは生計を維持されていた妻、子、孫、55歳以上の夫、父母、祖父母です。
受け取れる金額は、遺族基礎年金では68歳以下の方は年間816,000円に子の加算を加えた額、69歳以上の方は年間813,700円に子の加算を加えた額です。子の加算は第1子・第2子が各234,800円で第3子以降が各78,300円です(年金額は令和6年4月分からの金額)。
遺族厚生年金で受け取れる金額は死亡した人が厚生年金に加入していた期間の給与や賞与の金額から計算されます。計算式は以下の通りです。
{平均標準報酬月額×(7.125/1000)×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×(5.481/1000)×平成15年4月以後の被保険者期間の月数}×3/4
※被保険者期間が300月(25年)未満の場合は300月とみなして計算します。
※年金額は令和2年4月分からの金額です。
詳細な条件や金額については以下を参考にしてください。
-


遺族年金はいくらもらえる?受け取れる条件は?
一家の大黒柱が亡くなった場合、遺された家族には遺族年金が支給されます。収入保障保険などの死亡保険の保障額を決めるうえで遺族年金をいくら受け取ることができるのか知 ...続きを見る
みんなはどれくらいで設定している?
死亡保険金の設定の仕方が分かったところで、参考として世間の方々がどのような金額で死亡保険金額を設定しているのか紹介します。生命保険文化センター 2024(令和6)年度「生命保険に関する全国実態調査」(2025年1月発行)によると、世帯の死亡保険金額の平均は1,936万円、世帯主の死亡保険金額の平均は1,258万円、配偶者の死亡保険金額の平均は691万円です(いずれも全生保)。
ただし、必要な死亡保険金額というのは年齢やライフステージ、世帯年収によっても変わります。それぞれで分けた死亡保険金額についても紹介します。
世帯主年齢代別
| 世帯主年齢 | 世帯平均 | 世帯主平均 | 配偶者平均 |
|---|---|---|---|
| 29歳以下 | 1,747.0万円 | 1,071.1万円 | 882.5万円 |
| 30~34歳 | 2,526.1万円 | 2,000.6万円 | 948.5万円 |
| 35~39歳 | 2,450.4万円 | 1,761.5万円 | 869.2万円 |
| 40~44歳 | 2,474.8万円 | 1,676.4万円 | 823.4万円 |
| 45~49歳 | 2,313.3万円 | 1,508.7万円 | 754.0万円 |
| 50~54歳 | 2,504.4万円 | 1,624.2万円 | 775.0万円 |
| 55~59歳 | 2,102.5万円 | 1,329.2万円 | 704.3万円 |
| 60~64歳 | 1,910.1万円 | 1,096.5万円 | 628.1万円 |
| 65~69歳 | 1,492.2万円 | 766.7万円 | 470.0万円 |
| 70~74歳 | 1,114.0万円 | 598.5万円 | 412.4万円 |
| 75~79歳 | 1,158.5万円 | 661.0万円 | 429.7万円 |
出典:生命保険文化センター 2024(令和6)年度「生命保険に関する全国実態調査」(2025年1月発行)
世帯主では30代全半~50代前半がピークで老後が近づくにつれて死亡保険金額が減少していきます。配偶者の生活費や子供の教育費に必要な金額が次第に減少していくことが反映されています。
ライフステージ別
| ライフステージ | 世帯平均 | 世帯主平均 | 配偶者平均 |
|---|---|---|---|
| 夫婦のみ(40歳未満) | 1,369.0万円 | 961.5万円 | 648.8万円 |
| 夫婦のみ(40~59歳) | 1,930.2万円 | 1,350.1万円 | 646.2万円 |
| 末子乳児 | 2,411.4万円 | 1,742.1万円 | 843.4万円 |
| 末子保育園児・幼稚園児 | 2,660.9万円 | 1,784.0万円 | 944.9万円 |
| 末子小・中学生 | 2,430.3万円 | 1,668.3万円 | 773.2万円 |
| 末子高校・短大・大学生 | 2,504.9万円 | 1,612.5万円 | 792.9万円 |
| 末子就学終了 | 1,975.5万円 | 1,009.0万円 | 646.8万円 |
| 高齢夫婦有職(60歳以上) | 1,268.9万円 | 804.7万円 | 536.5万円 |
| 高齢夫婦無職(60歳以上) | 852.2万円 | 551.4万円 | 411.6万円 |
| その他 | 1,637.8万円 | 1,038.8万円 | 670.5万円 |
出典:生命保険文化センター 2024(令和6)年度「生命保険に関する全国実態調査」(2025年1月発行)
夫婦のみと比べて子供がいて末子が乳児や就学中の場合の方が死亡保険金額は大きくなっています。子供の教育費として必要な金額が反映されてのことだと考えられます。高齢夫婦については有職の方が死亡保険金額が大きいです。働いて得られる分の収入がなくなるということとより大きな金額の保険に加入する金銭的余裕があることが関係していると考えられます。
世帯年収別
| 世帯年収 | 世帯平均 | 世帯主平均 | 配偶者平均 |
|---|---|---|---|
| 200万円未満 | 876万円 | 618.2万円 | 490.9万円 |
| 200~300万円未満 | 949.6万円 | 760.6万円 | 513.9万円 |
| 300~400万円未満 | 1,285.3万円 | 986.8万円 | 629.7万円 |
| 400~500万円未満 | 1,477.7万円 | 1,245.8万円 | 763.7万円 |
| 500~600万円未満 | 1,823.8万円 | 1,462.6万円 | 789.9万円 |
| 600~700万円未満 | 2,026.9万円 | 1,512.8万円 | 798.5万円 |
| 700~1000万円未満 | 2,432.8万円 | 1,940.7万円 | 816.6万円 |
| 1000万円以上 | 3,090.4万円 | 2,495.1万円 | 786.0万円 |
| 不明 | 1,600.4万円 | 1,164.9万円 | 662.3万円 |
出典:生命保険文化センター 2024(令和6)年度「生命保険に関する全国実態調査」(2025年1月発行)
世帯年収が高くなるほど死亡保険金額も大きくなっています。生活水準が上がって必要な費用も高くなること、より大きな金額の生命保険に加入する金銭的余裕が出ることなどが関係していると考えられます。
終身保険だと保険料が高額になる場合は?
死亡保険の代表的なものには終身保険があります。しかし、終身保険は貯蓄機能も持っているため保険料が高めです。そのため、必要な死亡保障額をすべて終身保険で賄おうとすると保険料が高くなりすぎる場合があります。
そうした場合は掛け捨てで保険期間が決まっている定期保険やその一種である収入保障保険を組み合わせるとよいでしょう。葬儀費用などのいつ死亡しても必要となる分を終身保険で用意して、現役期間中の家族の生活費や子供の教育費などは定期保険や収入保障保険で上乗せするのです。
定期保険や収入保障保険は保険期間が決まっていて掛け捨ての保険なので、生涯保障で貯蓄としても使える終身保険より保険料が安くなっています。保険料が払いきれずに解約してしまっては意味がないので、こうした掛け捨ての保険も組み合わせて死亡保障を用意するとよいでしょう。
-

-
生命保険は終身保険と定期保険のどっちがいい?それぞれのメリット・デメリット
生命保険(死亡保険)には保障が一生涯続く終身保険と一定期間のみ保障を受けられる定期保険があります。この点だけ聞くと終身保険の方が良いような気がしますが、保障期間 ...続きを見る
また、終身保険の中でも低解約返戻金型のものを選べば保険料を少し抑えることができます。低解約返戻金型終身保険とは、保険料払込期間中の解約返戻金が通常の終身保険よりも低く抑えられている終身保険です。解約返戻金が低く抑えられている分、保険料が安くなっています。保険料を払っている途中の解約にはより気を付ける必要がありますが、保険料を抑える手段として検討してみるとよいでしょう。
-

-
低解約返戻金型終身保険とは?メリット・デメリットを紹介!
終身保険を検討していると「低解約返戻金型」と付いた商品を見かけたりすすめられたりすることがあります。これはいったいどのような終身保険なのでしょうか?また、どのよ ...続きを見る
まとめ
必要な死亡保険金額は各世帯によって異なります。紹介した死亡保険金額の平均を参考にしながらも、「必要保障額=遺された家族が必要となる金額-(遺された家族の収入+貯蓄)」という考えのもとで各世帯に合った保険金額を契約するようにしましょう。

-
著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。