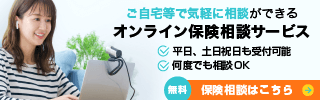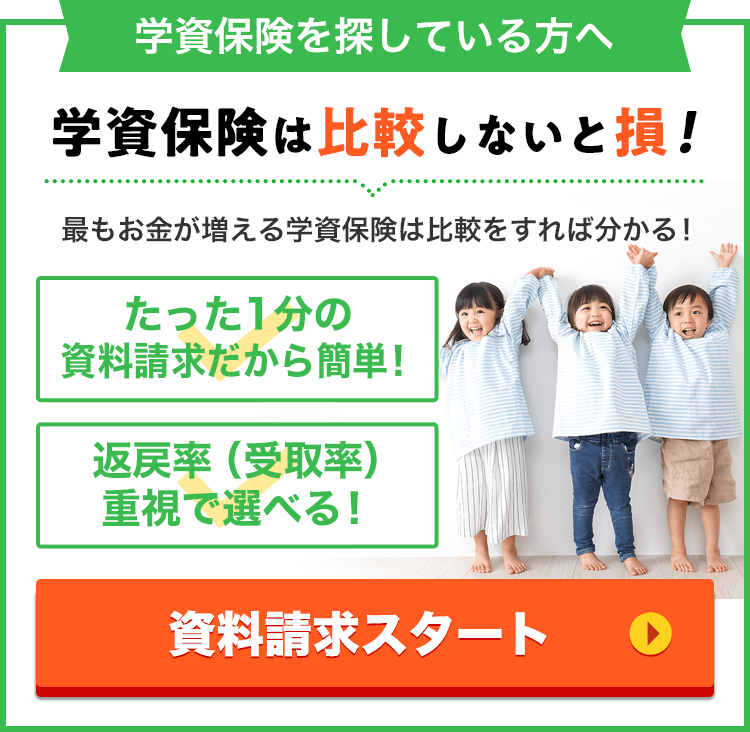学資保険の検討を後回しにしてしまい、我が子が小学生になってしまった…。子どもが小学生になってからでも学資保険に入れるのでしょうか?子どもが大きくなり学資保険に入りそびれてしまった方向けの教育資金の準備方法についても紹介します。
目次
小学生でかかる教育費

わが子が小学生になって出費が増え、これからかかる教育費が急に現実味を帯びてきたのではないでしょうか。家を購入して教育費の準備まで手が回らなかった…という方もいらっしゃるかもしれません。
公立小学校に6年通うとどのくらい教育費がかかるのか見てみましょう。
公立小学校の学年別教育費
| 学校教育費 | 学校給食費 | 学校外活動費 | 学習費総額 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1学年 | 159,953 | 39,313 | 199,002 | 398,268 |
| 第2学年 | 53,407 | 40,508 | 174,222 | 268,137 |
| 第3学年 | 53,125 | 39,184 | 203,152 | 295,461 |
| 第4学年 | 60,511 | 35,662 | 209,230 | 305,403 |
| 第5学年 | 72,312 | 39,105 | 243,020 | 354,437 |
| 第6学年 | 94,310 | 36,789 | 264,573 | 395,672 |
1年生は学校教育費が約16万円と全学年の中で一番多くなっています。これは文房具や楽器などの学用品やランドセルなどの通学用品が学校教育費に含まれているからです。公立小学校のため授業料や教科書代は無料ですが、1年生でも意外とお金がかかることが分かります。
高学年になると学校外活動費(学習塾やスポーツ等の習い事)が増えており、6年生では約26万4千円もかかっています。 学校外活動費は高学年になるほど多くなっていく傾向にあります。さらに中学校、高校、大学と進学するにつれ必要となる教育費はどんどん増えていきます。
小学生からでも教育費の準備を!
近年、子どもへの教育熱は低年齢化しています。例えば中学受験を考えている場合、4年生から通塾する家庭が多く、6年生ではテキスト代や特別講習を含めて100万円以上かかるといわれています。学習塾代以外でも通塾で必要な交通費や飲食代、受験時には受験料や入学金でまとまった金額が必要になります。
公立の中学校に進学する場合でも部活動等で出費も増え、運動部ではユニフォームや試合の遠征代といった費用がかかってくるでしょう。我が子が中学生・高校生になると、小学生だった時に比べてさらに貯蓄しにくくなってしまいます。
貯蓄が進んでいない方は今からでも教育資金の準備を始めていきましょう。
小学生から学資保険に入れる?

学資保険は子どもが小さいうちに入るイメージがありますが、小学生から学資保険に入ることも可能です。保険会社によっては学資保険に入れる子どもの年齢が6歳までになっていることが多いため、加入を希望する場合は早めに動いていきましょう。中には12歳まで入れるものもありますが、0歳に比べて加入できる商品が少なくなってしまうため注意が必要です。
加入する年齢が高くなると支払った総額よりも受け取れる金額が少なくなってしまうケースもあります。小学生から学資保険に入る場合には、メリット・デメリットを踏まえたうえで検討していきましょう。
小学生から学資保険に入るメリット
親にもしもの事があっても確実に教育資金を残せる
学資保険には、契約者である親が亡くなったり所定の高度障害状態になったりした場合は以降の払い込みが免除され、満期保険金を満額で受け取れるという死亡保障がついています。親としては、自分に万が一の事があっても確実に教育資金を確保できるので安心です。
節税になる
学資保険の保険料は生命保険料控除の対象になります。年末調整や確定申告をおこなうことで所得税や住民税が控除されるので節税につながります。
半強制的に貯蓄できる
子どもが大きくなってから教育資金を準備されている方の中には家計管理が苦手な方もいらっしゃるかもしれません。学資保険は途中で解約すると基本的に損をすることから解約に抵抗感が生まれます。払込が終わるまで口座引き落としにすれば半強制的に貯蓄ができるため貯蓄が苦手な方に向いています。
▼一括資料請求で保険会社を比較するワケ
▼一括資料請求で保険会社を比較するワケ
- ネットで簡単に資料請求!時間がない方にピッタリ
- 各社保障が違う商品から自分に合った保険を選べる
- 大切な資料を手元に残せる
小学生から学資保険に入るデメリット
保険料が高くなる
0歳から加入した人と6歳で加入した人では積み立てる期間が短いため、その分保険料が高くなります。
例えば、子どもが18歳になるまでに200万円を貯める場合、0歳からの18年間では毎月約9,259円必要なのに対し、6歳からの12年間では毎月約13,889円必要となってしまいます。加入する年齢が遅くなると毎月4,000円以上の負担が増えてしまいます。このように、学資保険に加入する年齢が高くなるほど毎月の保険料も高くなってしまうのです。
お金はあまり増えない
学資保険では保険会社が保険料を運用し、その収益を満期金に上乗せしています。運用期間が短いと収益も少なくなるため、0歳から加入している人と比べるとお金はあまり増えません。
また、契約する年齢によっては支払った総額よりも受け取れる金額が少なくなり、元本割れすることもあります。
親の年齢制限がある
万が一のことがあった時に以降の払い込みが免除される死亡保障があることから、契約者である親が高齢だと加入できない場合があります。
できるだけ元本割れをしないためには?
小学生になってから学資保険に加入した場合、大きくお金が増えることはあまり期待できません。一般的に、加入する子どもの年齢が高くなるほど返戻率が低くなるからです。少しでも多くのお金を受け取るために、この「返戻率」を上げる方法を紹介します。
返戻率とは
返戻率が100%を超えると支払った保険料より多く受け取れますが、返戻率が100%を下回ると支払った保険料より受け取れる金額が少ない「元本割れ」となってしまいます。
受け取り時期を延ばす
保険会社に保険料を預ける期間が長いほど返戻率が上がりやすくなります。18歳満期で満期金を受け取るより、22歳満期で満期金を受け取る方が返戻率が高くなります。
例として、学資保険で総額200万円受け取るとしたら、18歳満期では18歳時点で200万円受け取るのに対して、22歳満期では18歳から5年間40万円ずつ受け取るようなイメージです。22歳満期の場合は最も費用がかかる大学入学時は他の手段も併せて工面する必要があります。
年払いにする
保険料の払込方法を毎月ではなく、1年分をまとめて払う年払いにすれば返戻率がアップします。年に1回まとまったお金を準備できる方に向いています。
保険料の払込期間を短くする
保険料の払込期間を短くするほど、保険会社が運用できる期間も長くなるため返戻率が上がります。しかし、1回の保険料が上がることと、保険料をすべて支払い終わると死亡保障(死亡以後の保険料支払いが免除される)がなくなる、生命保険料控除を受けられる期間が短くなるというデメリットがあります。
無理は禁物
返戻率を高くするために、無理のある保険料を設定するのはおすすめできません。保険料を払いきれず学資保険を途中解約してしまうと、今まで支払ってきた保険料よりも解約返戻金は少なくなり本末転倒になってしまいます。満期まで支払い続けられる保険料を設定しましょう。
場合によっては、以下に紹介する他の方法で教育資金を準備することを考えてもよいかもしれません。
学資保険に入りそびれたらどうすればいい?
子どもが成長して学資保険に入りそびれてしまった方、加入できてもお金があまり増やせない方は他の方法で教育資金を用意していきませんか。
終身保険

学資保険の代わりに低解約返戻金型終身保険を利用してお金を貯めることもできます。終身保険は死亡保障が一生涯続く保険ですが、解約すると解約返戻金を受け取れます。保険料を払い終えた後も据え置く事で解約返戻率が上がり、教育資金が必要になったタイミングで解約することで解約返戻金を教育資金に充てることができます。
しかし、保険料を払い終わる前に解約すると学資保険以上に元本割れしてしまいます。早期に解約してしまうことがないようにしましょう。
-

-
子供の教育資金は学資保険と終身保険のどっちがいい?
妊娠中あるいは子供が生まれたら教育資金のために学資保険の検討を行う方は多いと思います。しかし、保険ショップなどで相談したら終身保険を勧められることもあります。子 ...続きを見る
外貨建て終身保険
終身保険の中には、支払った保険料を米ドル等の外貨で運用する外貨建ての終身保険があります。日本よりも海外の方が金利が高いことが多いため、米ドルベースの場合は外貨で運用するほうが高い返戻率になる傾向にあります。解約返戻金を受け取るタイミングで円安になっていると受取額が増えるため、有利なタイミングで解約することで多くの解約返戻金を受け取ることができます。
ただし為替リスクもあり、逆に解約時に円高になっていると元本割れすることもあるので注意しましょう。
-

-
米ドル建て終身保険は学資保険代わりに使える?メリット・デメリットは?
日本の低金利を背景に、学資保険を検討していたら米ドル建ての終身保険をすすめられるというケースが多くあるようです。はたして米ドル建ての終身保険は学資保険の代わりと ...続きを見る
NISA

投資信託や株式投資などで効率的に資産運用をする方法もあります。NISAを利用すれば1800万円まで非課税で運用できます。
投資先の株式や債券の価格が上昇すれば、大きくお金を増やすこともできますが、運用の結果マイナスになる可能性もあります。進学費用をすべて投資だけで準備してしまうと、いざ必要になった時に資金が足りなくなってしまう事態もありえますので注意が必要です。
-

-
学資保険の代わりにNISAで投資!これって本当?
子供の教育資金を貯める方法として昔から学資保険が多く使われてきました。しかし、長引く低金利の影響で昔と比べて学資保険の返戻率が下がってしまったことから、NISA ...続きを見る
まとめ
小学生になってから学資保険に入ると、支払った総額よりも受け取れる金額が少なくなってしまうことが多いです。親にもしものことがあった場合を考えると学資保険が安心ですが、他の方法で教育資金を用意していく事も考えてみませんか。
インズウェブでは学資保険の他にも上記で紹介した終身保険もまとめて資料請求ができます。教育資金に備えるためにぜひ利用してみませんか?