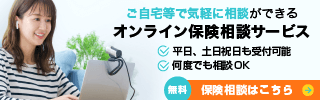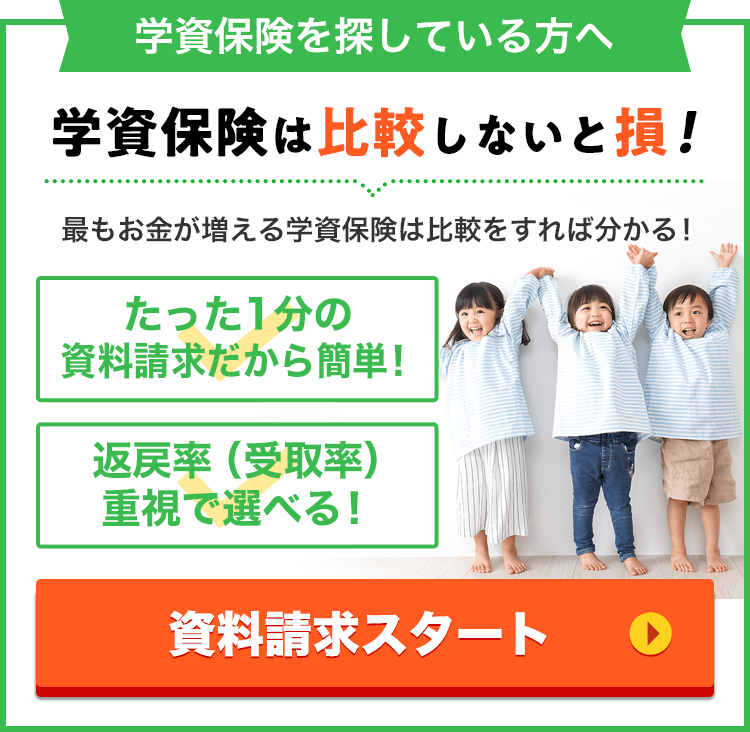子どもの教育費のうち、まとまったお金が必要になるのは大学入学時です。そのため、子どもが17,18歳になった時に学資保険の満期金を受け取る方が多いでしょう。受取金額として200万円に設定することが多いですが、この金額で大丈夫なのでしょうか?学資保険200万円では大学の費用には足りない可能性があります。その理由や実際にかかる費用、教育資金の準備方法を紹介します。
目次
200万円では足りない理由は?
大学入学時には入学金や授業料が必要ですが、特に初年度は教科書代や下宿する場合は部屋探しの費用もかかり、まとまったお金が必要になります。進学先によっては学資保険の200万円より多くの費用がかかる可能性があるのです。
例として国立大学と文系の私立大学を比べてみると、自宅から通学する場合は約110万円~150万円ほどで、学資保険で備えたお金で十分賄えそうです。しかし、私立大学で下宿をする場合は200万円を超えてしまう可能性があります。
| 大学初年度にかかる費用 | |
|---|---|
| 国立大学(自宅) | 1,130,700円 |
| 国立大学(下宿) | 1,633,900円 |
| 私立文系大学(自宅) | 1,507,740円 |
| 私立文系大学(下宿) | 2,010,940円 |
国立大学であれば余った分を翌年の授業料に充てる余裕はありそうですが、私立大学に通い一人暮らしを始める時には学資保険で準備した金額では足りなくなってしまうといえるでしょう。
大学初年度にかかる費用

大学初年度にかかる費用を詳しくみてみましょう。初年度は入学金を納付するため一番高く、国立大学では約80万円、文系の私立大学では約120万円、理系の私立大学では約150万円かかります。医歯系の私立大学は約480万円とさらに費用がかかります。授業料や施設設備費は毎年納付するため、2年生以降もまとまったお金が必要になります。
| 国立 | 私立文系 | 私立理系 | 私立医歯系 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 282,000 | 223,867 | 234,756 | 1,077,425 |
| 授業料 | 535,800 | 827,135 | 1,162,738 | 2,863,713 |
| 施設設備費 | 0 | 143,838 | 132,956 | 880,566 |
| 初年度の費用 | 817,800 | 1,194,840 | 1,530,450 | 4,821,704 |
出典 国立:国立大学等の授業料その他の費用に関する省令、私立:文部科学省「令和5年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金 平均額(定員1人当たり)の調査結果について」
初年度に必要なものとして、授業料とは別に教科書やパソコンも別途購入する必要があります。全国大学生活協同組合連合会の調査によると、パソコン・教科書・教材購入の費用として20万円以上かかるようです。
さらに地元から離れた大学に進学する場合は下宿費用も必要です。下宿をする場合は部屋探しの費用や家具・家電、インターネット回線、衣服等を含む新生活用品の購入費用が多くかかるため、さらに55万円ほど必要になります。
| 自宅生 | 下宿生 | |
|---|---|---|
| パソコン・教科書・教材購入の費用 | 224,200 | 258,700 |
| お部屋探しの費用 | - | 253,300 |
| 新生活用品購入費用 | 88,700 | 304,100 |
| 合計 | 312,900 | 816,100 |
出典:全国大学生活協同組合連合会「2024年度保護者に聞く新入生調査」
学資保険の受取金額を増やすのは注意!
大学入学時には授業料以外にも様々な費用がかかり200万円では足りない可能性があることが分かりましたが、学資保険の受取金額を増やせばいいのでは?と考える方もいるかもしれません。保険料を支払い続けられるのであればもちろん問題ないですが、以下のようなデメリットもあります。
保険料が高くなる
学資保険の受取金額は契約時に決めることができ、200万円以外にも300万円、500万円などと設定することもできます。ただ、受取金額を増やすということは毎月の保険料も増えてしまいます。受取金額を増やして500万円にすると2年目以降の学費も補えるため経済面では安心できそうですが、毎月の保険料は倍以上かかることになるでしょう。学資保険の多くは10年以上の長い期間をかけて保険料を支払っていきます。保険料の負担が重くなり途中で払えなくなると教育資金の用意ができなくなってしまいます。
途中解約すると元本割れになりやすい
学資保険の保険料が払えずに解約してしまうと、今まで払った保険料よりも少ない金額しか戻ってこない、つまり元本割れしてしまうことが多いです。子どもが大きくなるにつれて住宅や車のローン、部活動や進学塾などでまとまった出費が増えることもあるでしょう。そんな時に資金が足りないからといって学資保険を途中解約してしまうと損してしまう可能性が高いです。学資保険の保険料は無理なく支払い続けられる金額にしましょう。
▼一括資料請求で保険会社を比較するワケ
▼一括資料請求で保険会社を比較するワケ
- ネットで簡単に資料請求!時間がない方にピッタリ
- 各社保障が違う商品から自分に合った保険を選べる
- 大切な資料を手元に残せる
学資保険で足りない場合は?
学資保険で200万円を受け取る場合、進路によっては大学生活の学費には足りない可能性があります。そのため、学資保険だけでなく他の方法も併用して教育資金を貯めることを考えましょう。ここでは学資保険以外の準備方法を紹介します。
貯金
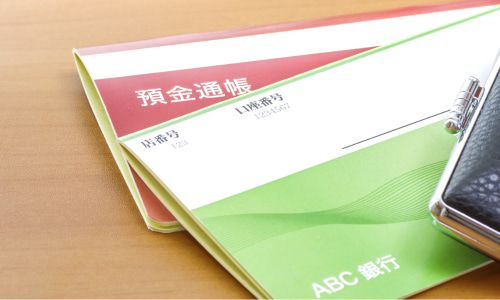
一番手軽にできる方法としてあげられるのが貯金です。国から支給される児童手当を全て貯金に回すと約240万円貯めることができます。急に大きな出費があった時でもすぐに引き出せますが、教育資金の分まで使い込んでしまったということがないように注意しましょう。教育資金用に口座を作り、生活費とは別に管理するのがおすすめです。
終身保険

終身保険は死亡保障が一生涯続きます。契約者に万が一の事があった場合には大きな金額を残すことができるので教育資金に備えられます。また、保険料の払い込み期間が終わった後に解約すれば、支払った保険料よりも多くの解約返戻金が受け取れます。払込期間を10年払済や15年払済に設定して、教育資金が必要になったタイミングで解約することで解約返戻金を教育資金に使うことができます。
学資保険は満期時にお金を受け取りますが、終身保険には満期がないため解約せずにそのまま置いておくこともできます。据え置き期間が長くなるほど返戻率が上がり、解約した際に受け取れる保険金も多くなる可能性があります。
しかし、保険料を払い終わる前に解約すると学資保険以上に元本割れしてしまいます。無理なく払っていける保険料になっているか十分に確認しましょう。
「死亡保障」と「貯蓄」の両方を重視するなら
NISA

株式や投資信託で資産運用をすることも教育資金を準備する方法の一つです。NISAを活用すれば投資で得た利益が非課税になり、非課税投資枠の範囲内であれば増えた金額をそのまま手にすることができます。そのため貯金や学資保険よりも効率良くお金を増やすことができます。
運用によって大幅にお金が増える可能性がある分、利益がマイナスになるリスクもあります。大学進学時など教育資金が必要になった時に相場が下落していると、資金が足りなくなる事態も起こりえます。投資だけで教育資金を貯めるのではなく、貯金や保険など他の方法と合わせて準備していきましょう。
教育ローン
家族の病気や介護、収入減などで家計に余裕がなくなり、経済的に学費を用意するのが難しくなることもあるかもしれません。そんな場合は教育ローンの利用を考えてみましょう。
国の教育ローンや銀行・信用金庫などの民間の教育ローンがあり、国の教育ローンは子ども1人につき350万~450万円まで借入できます。入学前・入学後問わずに申し込みができ、入学金や授業料だけでなく受験費用や教科書代、下宿代にも利用できるのが特徴です。
教育ローンは親が借りるローンのため借りた翌月から返済が始まります。在学中は利息のみの返済(元金据置)ができるものもありますが、無理のない返済計画を立てながら借入を検討しましょう。
奨学金
奨学金には返済必要の「給付型奨学金」と卒業後に返済する「貸与型奨学金」の2つの種類があります。奨学金によっては世帯収入や学力などの条件があり、給付型は条件が厳しいことが多いです。
返済が必要な貸与型は利息がかかるものもありますが、無利息のものもあります。卒業後は子ども本人が返済していくため、必要以上の奨学金を借りてしまうと将来大きな負担になってしまいます。奨学金を借りる際には返済期間や金額を踏まえたうえで慎重に考えましょう。
まとめ
大学入学時に合わせて学資保険の満期金を受け取る場合、200万円だけでは進学費用に足りない可能性があります。とはいえ、学資保険だけで大学の進学費用を準備しようとすると、保険料も高額になり解約のリスクが高くなってしまうので注意しましょう。教育資金を貯めるには貯金や保険、投資など複数の方法を組み合わせて準備することがおすすめです。それでも足りない場合には教育ローンや奨学金の利用を検討しましょう。