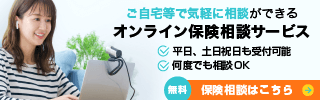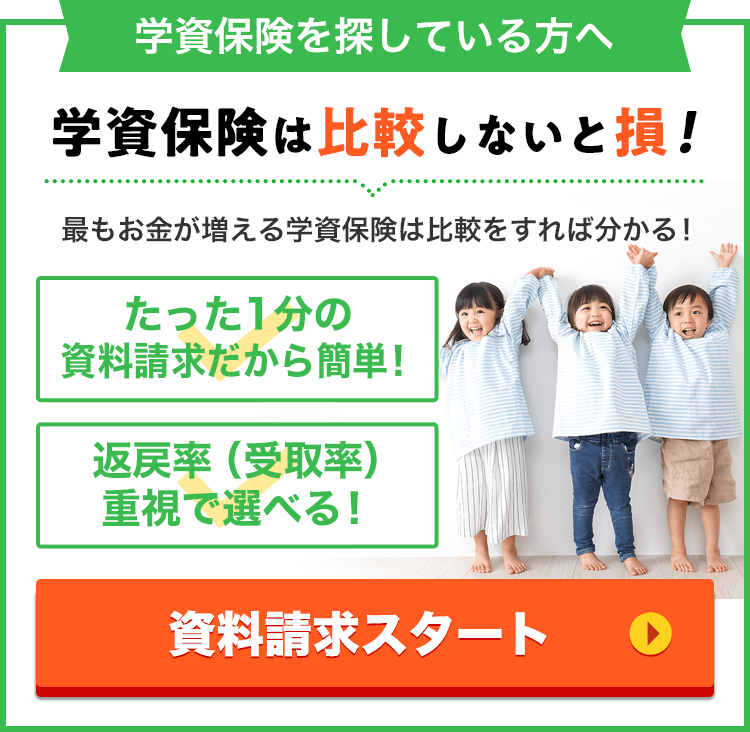子供の教育資金を貯める方法として昔から学資保険が多く使われてきました。しかし、長引く低金利の影響で昔と比べて学資保険の返戻率が下がってしまったことから、NISAを利用して投資で教育資金をためていくという人も増えています。過去の利回りの推移から考えるとNISAの枠内で投資をした方が学資保険よりも増えそうですが、本当にNISAを使ってためていくのがよいのでしょうか。
目次
NISAは学資保険の代わりになる?

まず最初に皆さんが気になるであろう、NISAは学資保険の代わりとして使えるのか、について記します。その答えとしては、「一定の条件を満たせば代わりとなる」です。
一定の条件というのは、以下の通りです。
- 投資に関する最低限の知識がある(調べることができる)
- 他に生命保険に加入しているなど、親が早期に死亡してしまったとしても教育資金を用意できる
- 大学入学時などお金が必要となるタイミングで損失が出ていても、他に教育資金に充てるお金の当てがある
投資に関する最低限の知識がある(調べることができる)
NISAを通じて行うのは投資なので、投資に関する最低限の知識は持っている必要があるでしょう。つみたて投資枠では初心者向けの商品もそろっていますが、投資は必ず利益が出るものではありませんし、そもそも全く知識がないと何をどのように購入すればよいかすらわからないでしょう。最初は知識がないのが当たり前なので調べながらでよいのですが、それも体が受け付けないというのなら投資はやめておいた方がよいでしょう。
親が早期に死亡してしまった場合の備えがある
学資保険では契約者(親)が死亡してしまった場合、その後の保険料の払い込みが免除され、満期時にも契約通りに保険金が支払われます。しかし、NISAでの投資にはそのような保障はありません。教育資金がたまり切っていない段階で親が死亡してしまった場合に子供の教育費をどうするのか考えておく必要があるでしょう。生命保険に加入しているなど、死亡時の備えができているのならばよいのですが、そうでなければNISAよりも先に死亡時の備えについて考えましょう。
NISAでの投資以外に資金の当てがある
NISAで行うのは投資なので、教育資金が必要となるタイミングで損失が出ているということも考えられます。大学入試の時期にリーマンショックの時のような株価の下落が発生する可能性も否定できません。そうした場合、足りない額を貯金などから補う必要があります。NISAでの投資に全振りするのではなく、リスクの小さい資産でも資金をためていく必要があります。
学資保険とNISAの違いは?
学資保険は保険料を積み立てて教育資金を準備する保険商品、NISAはその枠内で株式等の投資をして得た利益が非課税になる制度のことです。学資保険は堅実にお金を貯めることに、NISAはリスクを取ってお金を増やすことに向いているといえます。
学資保険とは
学資保険とは、契約時に決めた保険料を支払い、子どもが一定の年齢になるとお祝い金や満期金を受け取れる貯蓄型の保険です。学資保険の設定金額は人それぞれではありますが、受取総額200万円や300万円で契約している人が多いようです。
主に子どもが大学に進学する際の入学金や授業料を準備する目的で活用されることが多く、商品によっては幼稚園・小学校・中学校・高校入学の節目にもお祝い金を貰えるものがあります。
NISAとは
NISAとは、日本在住で18歳以上の人を対象に、合計1800万円までの枠内で購入した株式・投資信託等から得られた運用益や配当・分配金が非課税となる制度です。「つみたて投資枠」と「成長投資枠」があり、年間の投資上限額は「つみたて投資枠」で120万円、「成長投資枠」で240万円です。
2023年までは一般NISAとつみたてNISAで分かれて併用できませんでしたが、2024年からこれらが一本化された新しいNISAが始まりました。

「つみたて投資枠」で購入できるのは販売手数料がゼロ、信託報酬(投資信託を管理・運用してもらうための費用で、保有している間投資家が支払い続ける費用)が一定の基準以下などの要件を満たした商品が対象です。失敗しにくいように初めから商品が絞り込んであるのが特徴です。
一方、「成長投資枠」では一部の商品を除き上場株式や投資信託なども投資対象となります。つみたて投資枠との併用が可能で、限度額1,200万円以内であれば、成長投資枠を併用してつみたて投資枠の対象外の商品も購入も可能となります。
NISAで教育資金を貯めるメリット

大きく増える可能性がある
NISAでは購入した株式や投資信託などの価格が上昇すれば貯金や学資保険で貯めていくよりも大きく増やせる可能性があります。学資保険の返戻率は契約方法や年齢、商品などにもよりますが110%(払った保険料総額よりも10%多く保険金を受け取れる)でも高い水準と言われる程度です。子供が0歳で契約したとして18年間や22年間での結果なので、1年あたりで考えると1%を下回ります。
投資信託では投資先や世界的な経済状況にもよりますが、平均で年3%の利回りを得るというのも現実離れした数字ではありません。ただし、あくまでも過去の結果であって将来必ずこの利回りが保証されるというものではないことには注意してください。
途中で売却できる
NISAで運用した株式や投資信託などは好きなタイミングで売却できます。途中で家計が苦しくなった、塾や習い事などで大きな出費が必要となったという場合に、途中で売却したりすることもできます。さらに売却した分は翌年に1800万の枠から除かれて再利用できるので、柔軟に資産を活用することができます。
利益に税金がかからない
通常、株式や投資信託の売買で利益が出たら約20%の税金がかかりますが、NISAでは1800万円まで税金がかかりません。例えば100万円の利益が出たとすると、通常は約20万円の税金がかかり約80万円を受け取ることになりますが、NISAでは非課税となるため100万円の利益をそのまま受け取ることができます。
NISAで教育資金を貯めるデメリット
マイナスになることもある
NISAで行うのは投資なので、運用している途中でリーマンショックやコロナショックのような出来事があると大きくマイナスとなることもあります。例えばリーマンショックの発生時では、世界株式は米ドルベースで44%ほど下落しました。マイナスになっても投資を継続していれば将来的にプラスに戻ることは十分に考えられるのですが、子どもの進学費用は、「大学入学時に〇万円が必要」というように資金が必要となる年・金額が決まっています。つまりプラスになるまで待つことができません。
自分で商品を選ぶ必要がある
NISAでは自分でどの株や投資信託を購入するのか選ぶ必要があります。金融庁の基準を満たす商品に限られるので全体から見れば絞られているのですが、金融機関によってはつみたて投資枠でも100本以上の選択肢があるため、投資が初めての人はどれを選んだらよいのか悩んでしまう可能性があります。この点では学資保険よりも始めるハードルが高くなっているといえるでしょう。
学資保険で教育資金を貯めるメリット

親にもしもの事があっても確実に教育資金を残せる
学資保険には、契約者である親が亡くなったり所定の高度障害状態になったりした場合は以降の払い込みが免除され、満期保険金を満額で受け取れるという死亡保障がついています。親としては、自分に万が一の事があっても確実に教育資金を確保できるので安心です。
計画的に教育資金を準備できる
学資保険は契約時に月々支払う保険料や将来受け取れる金額、満期金等を受け取る時期が決まります。「〇年後に△万円が受け取れる」とあらかじめ分かっているため、資金計画を立てやすくなります。学資保険では、18歳の時点で一括で受け取るタイプや、幼稚園~大学入学のタイミングでお祝い金・満期金を受け取るタイプ、18歳から22歳まで毎年受け取るタイプなどがあります。
生命保険料控除を活用できる
学資保険の保険料は生命保険料控除の対象になります。あまり大きな金額ではありませんが、年末調整や確定申告をおこなうことで一定の額の所得控除を受けられるので所得税や住民税の負担を軽減することができます。
学資保険で教育資金を貯めるデメリット
お金はあまり増えない
学資保険は契約時の予定利率をもとにした返戻率で固定されるので、契約時が低金利の場合は返戻率も小さくなります。投資などよりもリスクが小さい分、増える額もそれほど大きくはならないのです。
インフレに弱い
学資保険の多くは契約した時の利率で固定され、将来受け取れる金額が決まっているためインフレに弱いといえます。教育資金が必要になるまでにインフレが起こって物価が上昇した場合、教育資金として必要な金額に足らなくなる可能性もありえます。例えば、18歳のときに200万円必要でそれに合わせて200万円受け取れる学資保険を契約していたとして、物価上昇で230万円必要となっても学資保険で受け取れるのは200万円のままです。
途中で解約すると元本割れする
途中で学資保険を解約してしまうと、ほとんどの場合支払った保険料よりも少ない金額しか戻ってきません。急に大きなお金が必要になって早期に解約してしまうことがないよう、月々の保険料が高くなり過ぎないように注意しましょう。あらかじめ決められたタイミングでしか保険金を受け取れないので、学資保険の他に自由なタイミングで使える教育資金を用意しておきましょう。
教育費の準備を「保険」で始める
学資保険とNISAを併用するのもあり
NISAでの投資はリスクはあるものの同じ元手で学資保険よりも多くの金額を用意しやすいです。しかし、子どもの教育資金をNISAだけで準備してしまうと、もし運用でマイナスになった場合に資金が足りなくなってしまう可能性があります。大きくお金を増やすこともできますが、市場価格の変動に左右されるため将来の資産がどうなるかは誰にもわかりません。逆に学資保険だけで教育資金を準備した場合、リスクは低いですが大きくお金を増やすことはできません。
そこで、学資保険とNISAのどちらかに限定するのではなく両方とも使うことも視野に入れてみるのもよいでしょう。NISAは月100円などの少額から始めることも可能です。学資保険で教育資金のベースを作りつつ、損をしても問題ない額をNISAで投資するというような方法もあります。
教育資金は準備が遅くなるほど大きな金額は用意しづらくなっていきます。特に学資保険は子どもの年齢が大きくなると加入しづらくなってしまうため、どちらにするのか長い間悩むよりかは早め早めに準備を進めていきましょう。

-
著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。