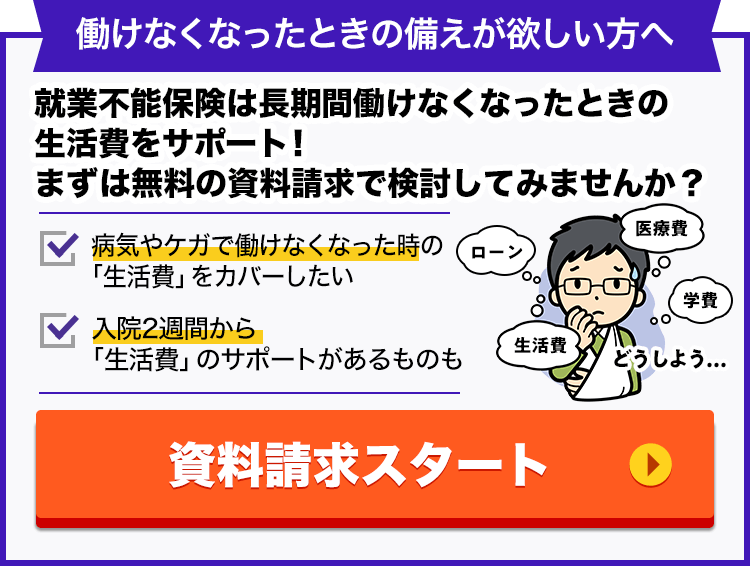昔から多くの保険が販売されてきましたが、最近注目を集めている保険の一つに就業不能保険があります。病気やケガで長期間働けなくなったときに備えるための保険なのですが、実際のところどれくらいの人が加入しているのでしょうか?
目次
どんな保険が必要か、いくらの保障が必要なのか分からない方へ
簡単な質問に答えるだけで、あなたに必要な備えと保障金額がすぐにわかります。
最短1分、無料でご利用可能ですので、ぜひお試しください!
\自分に必要な保障がわかる!/
就業不能保険の加入率は?
就業不能保険の加入率について、生命保険文化センター「2024(令和6)年度『生命保険に関する全国実態調査』」より紹介します。同調査は3年ごとに行われていますが、「生活障害・就業不能保障保険、生活障害・就業不能保障特約」の加入率についての調査は令和3年の調査から新たに追加されており、その注目度合いがうかがい知れます。
同調査によると、民保加入世帯(かんぽ生命を除く)の「生活障害・就業不能保障保険、生活障害・就業不能保障特約」の世帯加入率は17.2%です。世帯員別にみると、世帯主は14.9%、配偶者は6.4%となっています。
ただし、就業不能保険はその性格上、老後になってからは必要性の薄い保険です。また、他に家計を支える人はいるか、養うべき人がいるかによってもその必要性の度合いは変わってきます。そこで、世帯主の年齢別の加入率とライフステージ別の加入率も紹介します。
世帯主年齢代別加入率
| 世帯主年齢代 | 標本サイズ | 世帯加入率 |
|---|---|---|
| 29歳以下 | 64 | 20.3% |
| 30~34歳 | 127 | 28.3% |
| 35~39歳 | 285 | 26.7% |
| 40~45歳 | 299 | 22.7% |
| 45~49歳 | 332 | 25.0% |
| 50~54歳 | 384 | 25.5% |
| 55~59歳 | 318 | 20.8% |
| 60~64歳 | 320 | 12.8% |
| 65~69歳 | 297 | 7.4% |
| 70~74歳 | 316 | 4.7% |
| 75~79歳 | 202 | 4.0% |
| 80~84歳 | 102 | 2.0% |
| 85~89歳 | 29 | 3.4% |
| 90歳以上 | 10 | 10.0% |
出典:生命保険文化センター「2024(令和6)年度『生命保険に関する全国実態調査』」
世帯主年齢代別にみると、30~34歳が28.3%と最も加入率が高くなっています。
ライフステージ別加入率
| ライフステージ | 標本サイズ | 世帯加入率 |
|---|---|---|
| 夫婦のみ(40歳未満) | 43 | 32.6% |
| 夫婦のみ(40~59歳) | 200 | 19.5% |
| 末子乳児 | 98 | 23.5% |
| 末子保育園児・幼稚園児 | 317 | 21.8% |
| 末子小・中学生 | 550 | 27.1% |
| 末子高校・短大・大学生 | 308 | 24.4% |
| 末子就学終了 | 661 | 14.7% |
| 高齢夫婦有職(60歳以上) | 364 | 6.9% |
| 高齢夫婦無職(60歳以上) | 240 | 2.1% |
| その他 | 304 | 11.2% |
出典:生命保険文化センター「2024(令和6)年度『生命保険に関する全国実態調査』」
ライフステージ別にみると、末子が就学前や就学中の家庭で加入率が高くなっています。現役世代であっても夫婦のみの世帯や末子が就学終了している世帯では加入率が14~19%程度にとどまっています。長期間働けなくなったときのリスクの大きさが加入率の差に表れているのでしょう。
就業不能保険を選ぶ際の注意点は?
就業不能保険は昔から販売されてきた死亡保険や医療保険と比べて歴史が浅く、商品ごとの差異が大きいところがあります。そのため、加入を検討する場合は商品ごとの内容をよりしっかりと確認する必要があります。どのような点に注意して選ぶのがよいのか紹介します。
「働けない」がどのような場合を指すのか
就業不能保険は病気やケガで長期間働けない状態(就業不能状態)になった場合に給付金を受け取れますが、商品によって「働けない」というのがどのような状態を指すのか異なっています。自分でいくら働けないと思っていても保険会社が定める条件に合致しなければ給付金は支払われませんので注意して確認する必要があります。
差異として大きな部分ではうつ病などの精神疾患を対象とするか否かがあります。全体でみると精神疾患を保障対象としている就業不能保険は多くありません。しかし、後発の商品ほど精神疾患にも対応している傾向にあります。うつ病の場合も保障を受けたいという場合はどのような場合が「働けない」状態に当たるのかしっかりと確認しておきましょう。
-

-
就業不能保険でうつなどの精神疾患は保障される?
働けなくなる理由の多くはうつ病などの精神疾患といわれています。また、入院するほどの精神疾患は入院日数が多くなりがちで、長い間働くことができません。長期間働けない ...続きを見る
支払対象外期間はどれだけか
長期間働けない場合の「長期間」というのが具体的にどれだけかというのも確認すべきポイントです。就業不能保険では支払対象外期間(免責期間)が60日や180日などと設定されていることが多いです。就業不能状態がこの期間を超えて継続している場合に給付金が支払われます。支払対象外期間も給付金を受け取るための重要な条件の一つなので、しっかりと確認しておく必要があるでしょう。
いつまで給付金を受け取れるのか
給付金をいつまで受け取れるのかも商品によって異なります。契約期間中は就業不能状態が解消されるまで給付金が支払われ続けるという商品もあれば、就業不能状態が継続していても受け取れる期間が決まっている商品もあります。いつまで給付金を受け取ることができるのかということもしっかり確認しておきましょう。
まとめ
生命保険文化センター「2024(令和6)年度『生命保険に関する全国実態調査』」によると、就業不能保険の世帯加入率は同調査によると、民保加入世帯(かんぽ生命を除く)の「生活障害・就業不能保障保険、生活障害・就業不能保障特約」の世帯加入率は17.2%です。ただし、これは高齢者なども含んだ加入率であり、現役世代に限った場合の加入率は30%ほどです。
就業不能保険は死亡保険や医療保険と比べると歴史が浅く、まだ商品ごとの差異も大きい状態です。加入を検討する場合にはどのような場合に給付金を受け取れるのか、いつまで給付金を受け取れるのかということに気をつけて各商品を比較してみるとよいでしょう。

-
著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。