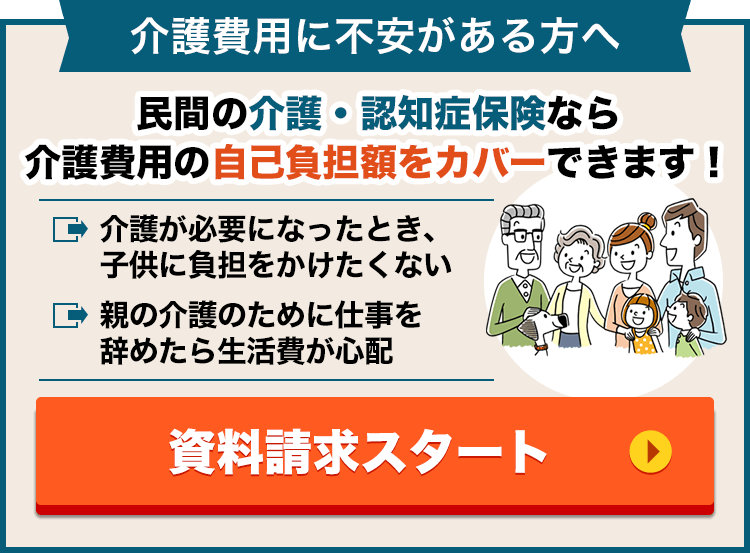たとえば親の介護が必要になった時、介護にかかる費用は誰が負担するものなのでしょうか。また、介護生活にかかるお金はどうやって用意すれば良いのでしょうか。大まかにかかる費用を把握するためにも、まずは公的介護保険で受けられる補助やサービスを把握しておきましょう。
目次
どんな保険が必要か、いくらの保障が必要なのか分からない方へ
簡単な質問に答えるだけで、あなたに必要な備えと保障金額がすぐにわかります。
最短1分、無料でご利用可能ですので、ぜひお試しください!
\自分に必要な保障がわかる!/
介護にはどれぐらいの年数・費用がかかる?
介護期間は平均4年7ヶ月
| 6ヶ月 未満 | 6ヶ月~1年 未満 | 1~2年 未満 | 2~3年 未満 | 3~4年 未満 | 4~10年 未満 | 10年 以上 | 不明 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1% | 6.9% | 15.0% | 16.5% | 11.6% | 27.9% | 14.8% | 1.3% | 55.0ヶ月 (4年7ヶ月) |
介護費用は平均月額9.0万円。更に一時金が必要になるケースも
月額
| 支払った 費用はない | 1万円 未満 | 1万~5万円 未満 | 5万~10万円 未満 | 10万円~15万円 未満 | 15万円 以上 | 不明 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 5.9% | 28.4% | 14.3% | 15.9% | 19.3% | 16.1% | 9.0万円 |
一時的な費用の合計
| かかった 費用はない | 15万円 未満 | 15万~50万円 未満 | 50万~100万円 未満 | 100万~200万円 未満 | 200万円 以上 | 不明 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5% | 24.0% | 16.3% | 7.2% | 8.2% | 4.7% | 22.0% | 47万円 |
介護に要した費用(公的介護保険サービスの自己負担費用含む)は、月々の費用の平均が9.0万円、一時的な費用の合計が47万円となっています。
一時的な費用とは、要介護者の状態にあわせて歩行の補助のために家の中に手すりを付けたり、車椅子用にバリアフリーの工事をしたりと、住宅改造にかかるお金や、介護用ベッドの購入費など、介護生活のためにかかった費用を指します。
介護費用は誰が負担するもの?
介護費用は要介護者が負担するもの
介護費用は原則的に要介護者自身の収入や預貯金からまかなうものです。
しかし中には、要介護者自身が十分な資金を用意していないというケースもあります。そうした場合、同居の家族や要介護者の子ども等が費用を負担しなければならない可能性が生じます。介護費用が足りない場合、誰がどのようにいくら負担するのかきちんと話し合って決めましょう。
要介護者の子どもが費用を負担する場合はトラブルに注意
厚生労働省の調査では、家庭内で介護者が出た場合、約半数の家庭で同居の家族が介護を担当しているようです。※
予期しないタイミングで親が病気やケガをして要介護状態になってしまった場合、事前に十分に準備をしていないことも多く、介護生活になってから思わぬトラブルが起きる可能性があります。
介護する側の生活が苦しくなる
要介護状態や要支援状態になってしまった場合、どの程度であるか市町村に設置される介護認定審議会により判定されます。介護レベルが高ければ高いほど要介護者が生活するために必要な介護の必要度合いも高くなり、介護をする側の負担も大きくなります。
特に要介護5になるとほとんど寝たきりの状態ですので、日常生活のほとんどすべてを常時介護していないと生活できません。
そうした人を同居の家族や要介護者の子どもだけで介護しようとすると、介護にかける時間や労力を捻出するために従来の生活サイクルを変えなければいけなくなったり、仕事をしながら介護をするのが難しくなったりします。そんな状況で更に介護にかかる出費まで子どもが負担することになれば、経済的なストレスも重なり介護する側が体調を崩してしまう可能性があります。
兄弟姉妹間で負担に差が出る
要介護者の子どもが複数人いる場合、誰が介護をするのか、金銭負担をどうするのかといった問題が生じます。
遠方に住んでいると介護をするために通うのに時間やお金がかかるため、どうしても同居の子どもや近くに住んでいる子どもが介護を引き受けざるを得ない状況に陥りがちです。なんとなく状況に流されて役割を決めたり、事前に全員が納得できるまで話し合って役割分担や費用負担について決めておかないと、
- 時間や労力を割いて介護をしたのに遺産相続の割合に加味してもらえない
- 介護をしていない兄弟姉妹が口だけ出してくる
- 何かと理由をつけて援助や介護の協力を拒否される
といったトラブルが起きてしまうことも。こうしたトラブルが起きると、それまで仲の良かった兄弟姉妹間でも軋轢を生み不仲になってしまう可能性は十分にありえます。
※厚生労働省「国民生活基礎調査の概況」 2022年
公的介護保険を活用しよう
介護にかかる時間やお金など、考えだすと不安は尽きないかもしれません。ですがお金に関しては、介護にかかる費用をすべて要介護者が負担する必要はありません。
公的介護保険の給付を受けたり、日々の介護はデイサービスやデイケアを活用するなど、公的介護保険制度でどのような支援を受けられるのか把握しておきましょう。
公的介護保険の給付
公的介護保険は、要介護認定を受けた利用者が「1~3割」の利用料を支払うことで「現物給付」による介護サービスを受けることができます。(一部現金による給付あり)
- 40~64歳の人や住民税が非課税の人などは所得に関わらず1割負担
- 65歳以上(第1号被保険者)で合計所得金額が160万円(単身で年金収入のみの場合の目安額280万円)以上の人は自己負担2割
- 65歳以上(第1号被保険者)で合計所得金額が220万円(単身で年金収入のみの場合の目安額340万円)以上の人は自己負担3割
※合計所得金額とは、収入から公的年金等控除などを差し引いた後で、基礎控除や配偶者控除などを差し引く前の金額です。
-

-
介護保険の自己負担はどうやって決まるの?
介護保険の自己負担割合は、所得に応じて1割から3割までのいずれかとなっています。介護サービスを利用する時に、自分の自己負担割合は、介護保険負担割合証に記載されて ...
介護サービスの利用
要介護認定を受けると居宅サービスや地域密着型サービスを受けられるようになります。
居宅サービス
居宅サービスは要介護者が現在の住居に住んだまま提供を受けられる介護サービスです。短期入所介護(ショートステイ)や、通所介護(デイサービス)、訪問介護(ホームヘルプサービス)等が利用できます。
ショートステイは要介護者を短期間宿泊させてもらい、食事や排せつの介助、リハビリ、レクリエーションなどを提供してもらえます。用事があって数日間預かってほしい時や介護する人の気分転換等、必要な時に利用しましょう。自宅での入浴させるのが難しい時はデイサービスや訪問介護でやってもらうことも可能です。
地域密着型サービス
居宅サービスと同様に介護保険制度に含まれる介護サービスで、認知症患者や高齢者が住み慣れた地域で生活できるようにサポートしてくれます。一つの事業者と契約するだけで通いを中心としながら夜間の巡回訪問やデイサービス、ショートステイなど様々なサービスを利用できるため、スタッフと顔なじみになり要介護者の健康状態も把握してもらえるなど、安心感が得られるというメリットがあります。
居宅サービスと異なり、特別養護老人ホームや有料老人ホームに入居する要介護者も生活支援や各種介護を提供してもらえます。
足りない分は民間介護保険でカバー
民間介護保険は公的介護保険では対象とならない年齢での保障が欲しい場合や、介護サービス費用以外の費用、公的介護保険の自己負担部分を補てんするために加入します。公的介護保険の給付は40歳以上が対象となるため、40歳未満で要介護状態になってしまった場合は民間介護保険が助けになります。
また、公的介護保険が給付されても収入に応じて自己負担分は発生するため、要介護者に十分な備えがなく、子どもが介護費用を負担しなければならない場合等は民間介護保険の給付金で支出をカバーしても良いでしょう。
-

-
民間介護保険とは?公的介護保険との違いとその必要性
日本は65歳以上の人口の割合が全人口の21%を超える「超高齢社会」です。その中で介護は多くの人にとって避けられない問題となっています。社会保障制度として公的な介 ...