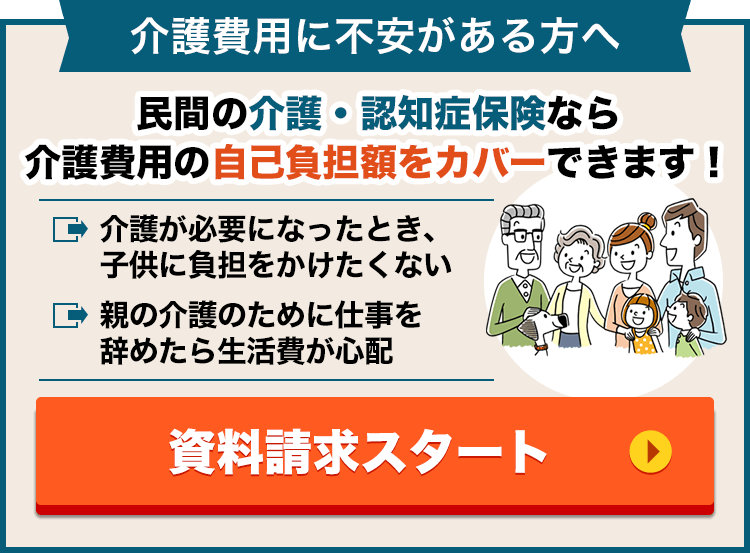日本は65歳以上の人口の割合が全人口の21%を超える「超高齢社会」です。その中で介護は多くの人にとって避けられない問題となっています。社会保障制度として公的な介護保険がありますが、民間の保険会社も介護保険を販売しています。民間の介護保険は公的介護保険とどのような違いがあるのでしょうか。また、民間の介護保険は必要なのでしょうか。
どんな保険が必要か、いくらの保障が必要なのか分からない方へ
簡単な質問に答えるだけで、あなたに必要な備えと保障金額がすぐにわかります。
最短1分、無料でご利用可能ですので、ぜひお試しください!
\自分に必要な保障がわかる!/
民間介護保険とは
民間介護保険とは、民間の保険会社が提供する介護保険です。40歳から強制加入となる公的介護保険を補う目的で加入することとなります。公的介護保険では対象とならない年齢での保障が欲しい場合や介護サービス費用以外の費用、公的介護保険の自己負担部分を補てんするために加入します。
民間介護保険と公的介護保険の違い
民間の介護保険と公的介護保険の違いについてまとめます。加入義務や給付方法、給付条件などに違いがあります。
| 公的介護保険 | 民間介護保険 | |
|---|---|---|
| 加入義務 | あり(40歳以上) | なし(任意加入) |
| 加入条件 | 65歳以上の人 40歳~65歳未満の健康保険加入者 |
各保険会社の規程による |
| 給付方法 | 現物給付 (所定の介護サービス) |
現金給付 (一時金、年金など方法は契約内容による) |
| 給付条件 | 65歳以上の場合は要支援状態・要介護状態になった場合 40歳~64歳の場合は老化が原因とされる特定疾病で要支援状態・要介護状態になった場合 |
保険会社との契約内容による 公的介護保険に準じる場合と保険会社が独自に定めた基準による場合がある |
民間介護保険は民間の保険会社によって運営される保険なので、統一的に記載できない部分がありますが、任意加入の保険であり、所定の状態になった場合に現金での給付を受けられるという点が公的介護保険との大きな違いです。
どれくらいの人が介護が必要になる?
要支援・要介護と認定された人を介護が必要な人と定義した場合、令和4年度末現在で約694万人が介護が必要となっています。(令和4年度 介護保険事業状況報告(年報)より)694万人のうち、65歳以上の人は681万人(男性213万人、女性468万人)、40歳~65歳未満の人が13万人(男性7万人、女性6万人)です。65歳以上に限定すると、全国平均で19.4%の人が介護が必要となっています。
| 区分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40歳以上65歳未満 | 12 | 19 | 21 | 27 | 19 | 16 | 16 | 130 |
| 65歳以上70歳未満 | 30 | 32 | 38 | 36 | 25 | 23 | 20 | 203 |
| 70歳以上75歳未満 | 80 | 80 | 97 | 86 | 62 | 57 | 44 | 507 |
| 75歳以上80歳未満 | 149 | 134 | 175 | 134 | 96 | 88 | 64 | 840 |
| 80歳以上85歳未満 | 267 | 226 | 319 | 222 | 160 | 145 | 98 | 1,438 |
| 85歳以上90歳未満 | 282 | 269 | 419 | 307 | 234 | 215 | 138 | 1,863 |
| 90歳以上 | 164 | 199 | 377 | 349 | 324 | 342 | 208 | 1,964 |
| 合計 | 985 | 959 | 1,446 | 1,160 | 920 | 886 | 587 | 6,944 |
| 構成比 | 14.2% | 13.8% | 20.8% | 16.7% | 13.2% | 12.8% | 8.5% | 100.0% |
※数値は千人未満を四捨五入しているため計に一致しない場合があります。
※保険者が国民健康保険団体連合会に提出する受給者台帳を基にしたものであり、提出後に要介護度が遡って変更になる場合があります。
参考:要支援・要介護認定の身体状態の目安
| 介護認定 | 身体状態の例 |
|---|---|
| 自立(非該当) | 歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態 |
| 要支援1 |
要介護状態とは認められないが、社会的支援を必要とする状態 食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、立ち上がりや片足での立位保持などの動作に何らかの支えを必要とすることがある。入浴や掃除など、日常生活の一部に見守りや手助けが必要な場合がある。 |
| 要支援2 |
生活の一部について部分的に介護を必要とする状態 食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、ときどき介助が必要な場合がある。立ち上がりや歩行などに不安定さがみられることが多い。問題行動や理解の低下がみられることがある。この状態に該当する人のうち、適切な介護予防サービスの利用により、状態の維持や、改善が見込まれる人については要支援2と認定される。 |
| 要介護1 | |
| 要介護2 |
軽度の介護を必要とする状態 食事や排泄に何らかの介助を必要とすることがある。立ち上がりや片足での立位保持、歩行などに何らかの支えが必要。衣服の着脱は何とかできる。物忘れや直前の行動の理解の一部に低下がみられることがある。 |
| 要介護3 |
中等度の介護を必要とする状態 食事や排泄に一部介助が必要。立ち上がりや片足での立位保持などがひとりでできない。入浴や衣服の着脱などに全面的な介助が必要。いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある。 |
| 要介護4 |
重度の介護を必要とする状態 食事にときどき介助が必要で、排泄、入浴、衣服の着脱には全面的な介助が必要。立ち上がりや両足での立位保持がひとりではほとんどできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。 |
| 要介護5 |
最重度の介護を必要とする状態 食事や排泄がひとりでできないなど、日常生活を遂行する能力は著しく低下している。歩行や両足での立位保持はほとんどできない。意思の伝達がほとんどできない場合が多い。 |
出典:公益財団法人 生命保険文化センター「公的介護保険で受けられるサービスの内容は?」
なお、実際の認定は高齢者の心身の状況調査及び主治医意見書に基づくコンピュータによる要介護認定基準時間の算出結果(一次判定)と主治医の意見書等に基づき行われます。
介護に必要に費用は?
介護が必要となった場合、どれくらいの費用が必要になるのでしょうか。生命保険文化センター2024(令和6)年度「生命保険に関する全国実態調査」によると、介護に要した費用(公的介護保険サービスの自己負担費用を含む)は、住宅改造や介護用ベッドの購入などの一時費用の合計が平均47万円、月々の費用が平均9.0万円です。また、同出典によると、介護期間の平均は55.0カ月(4年7カ月)となっています。ここから、介護に必要な費用は合計で47万円+9.0万円/月×55.0カ月=542万円となります。
一度に500万円を超える費用が必要になるわけではありませんが、介護費用としてこれくらいの支出をして大丈夫なように家計を設計する必要があります。また、介護の平均期間で計算しましたが、介護期間が長引くほど必要な介護費用も増えていきます。同じ調査では介護期間が10年以上と回答した人が14.8%も存在しています。
<介護期間>
| 6カ月未満 | 6カ月~1年未満 | 1~2年未満 | 2~3年未満 | 3~4年未満 | 4~10年未満 | 10年以上 | 不明 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1% | 6.9% | 15.0% | 16.5% | 11.6% | 27.9% | 14.8% | 1.3% | 55.0ヵ月 (4年7ヵ月) |
出典:生命保険文化センター2024(令和6)年度「生命保険に関する全国実態調査」
民間の介護保険は必要?
結果的に民間の介護保険は必要なのでしょうか。65歳以上になると何らかの介護が必要になる可能性は十分に考えられるレベルとなっています。このときに必要な介護費用を自分が持っている資産や収入で賄いきれる場合は民間の介護保険の必要性は薄いでしょう。
一方で、介護費用を十分に用意できそうにない人や介護状態になった時に面倒を見てくれる人がいない人、また、例外を除き公的介護保険を利用できない64歳以下で要介護状態になった場合に介護費用を用意できない人は民間の介護保険について検討してみるとよいでしょう。介護保険の検討のために、まずは資料請求をしてみることをおすすめします。

-
著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。