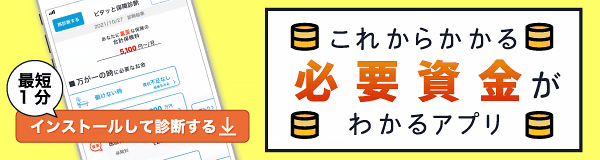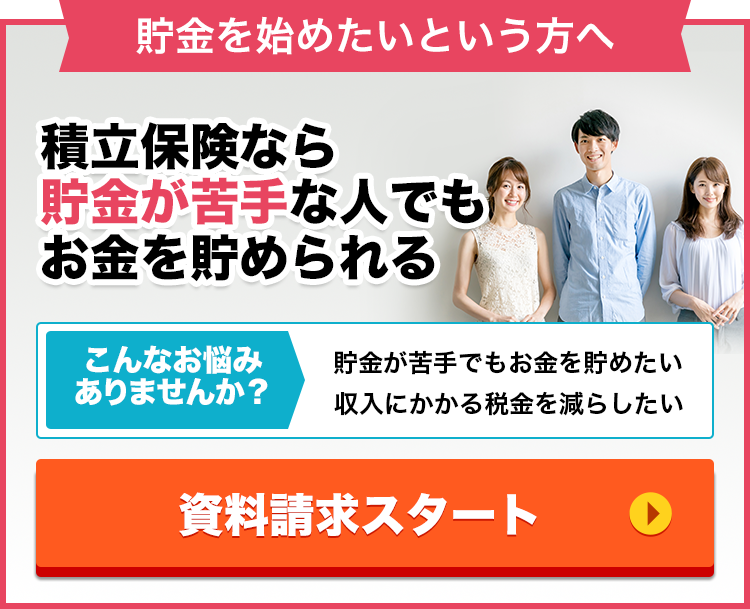「将来のことを考えて貯金を始めたいけど、どれくらいの金額を貯金に回せばいいの?」、とお悩みの方はいませんか?総務省統計局の「家計調査」から世間の人々は収入のうちの何割を貯蓄に回しているのか探ってみたいと思います。
どんな保険が必要か、いくらの保障が必要なのか分からない方へ
簡単な質問に答えるだけで、あなたに必要な備えと保障金額がすぐにわかります。
最短1分、無料でご利用可能ですので、ぜひお試しください!
\自分に必要な保障がわかる!/
年齢代別の貯蓄割合
年齢代別に収入からどれだけの割合で貯蓄に回しているのか紹介します。
| 世帯主の年齢 | 29歳以下 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯人員 | 1.28 | 2.56 | 3.15 | 2.45 | 2.26 | 1.95 |
| 可処分所得 | 320,677 | 440,381 | 530,323 | 488,452 | 382,690 | 327,406 |
| 預貯金純増 | 133,180 | 174,090 | 189,889 | 147,365 | 110,816 | 111,140 |
| 預貯金純増率 | 41.5% | 39.5% | 35.8% | 30.2% | 29.0% | 33.9% |
| 金融資産純増 | 140,806 | 191,326 | 214,285 | 176,028 | 113,782 | 109,800 |
| 金融資産純増率 | 43.9% | 43.4% | 40.4% | 36.0% | 29.7% | 33.5% |
出典:総務省統計局「家計調査」(2024年)総世帯のうちの勤労者世帯
上の表で可処分所得とは、収入から税金や社会保険料などを差し引いた金額で、いわゆる手取り収入のことです。
20代のうちは独身の人が多く、子供の教育費や住宅ローンなどの支出もないことから40%と多くの金額を貯蓄に回していることがわかります。一方で住宅ローンの支払いや子供の教育費などが多くかかってくると考えられる40代・50代は30%台の貯蓄率となっています。
年間収入別の貯蓄割合
年齢別の貯蓄割合を紹介しましたが、年収によって貯蓄のしやすさは異なるでしょう。月の手取りが25万円の人と40万円の人で同じように手取りの30%を貯蓄に回した場合、手取り25万円の人は7.5万円を貯蓄に回すことになるので残りの生活費は17.5万円ですが、手取りが40万の人は12万円を貯蓄に回すので残りは28万円です。そこで、年収別の貯蓄割合も調べてみました。
| 年間収入 | ~367万 | 367万~526万 | 526万~680万 | 680万~898万 | 898万~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 世帯人員 | 1.38 | 1.95 | 2.62 | 3.02 | 3.25 |
| 可処分所得 | 228,775 | 330,943 | 403,848 | 515,405 | 754,011 |
| 預貯金純増 | 66,220 | 102,233 | 134,991 | 167,837 | 291,476 |
| 預貯金純増率 | 28.9% | 30.9% | 33.4% | 32.6% | 38.7% |
| 金融資産純増 | 71,114 | 115,631 | 149,084 | 188,373 | 327,708 |
| 金融資産純増率 | 31.1% | 34.9% | 36.9% | 36.5% | 43.5% |
出典:総務省統計局「家計調査」(2024年)総世帯のうちの勤労者世帯
区切りとなっている年間収入が中途半端なのは各区分における世帯数を合わせるためです。
年収が多くなるほど貯蓄に回す割合も多くなる傾向が見て取れると思います。社会情勢などによっても貯蓄率は変わるので調査年によってはこれよりも少なくなる年も多くなる年もあります。収入が少なくて厳しい場合は手取りの10~20%前後、そこそこの年収がある場合は手取りの20~30%前後、年収が多い場合は手取りの30~40%前後を目安に貯蓄に回すのが良いでしょう。
積立保険で貯蓄を増やす!
そんなに貯蓄できない…という場合は?
手取りの20%や30%もの金額は貯蓄に回せない…という場合は、まずは手取りの10%を貯蓄に回せるように努力してみましょう。世の中には将来に向けての貯金が全くないという家庭もたくさんありますから、一歩リードできます。
| 世帯主の年齢 | 単身世帯 | 二人以上世帯 |
|---|---|---|
| 20歳代 | 43.9% | 36.8% |
| 30歳代 | 34.0% | 28.4% |
| 40歳代 | 40.4% | 26.8% |
| 50歳代 | 38.3% | 27.4% |
| 60歳代 | 33.3% | 21.0% |
出典:金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査(令和5年)」
-

-
貯金ゼロから脱却する方法は?
毎月の給料はすべて使ってしまって貯金ゼロ、このままではいけないと感じているけれどもどうやってお金を貯めたらいいのか分からない、という方はいませんか?貯金ゼロから ...続きを見る
10%でも貯蓄するのは難しいという場合は、まずは月の支出の内訳を把握して削れるものはないのか考えてみましょう。月の支出を把握するには家計簿アプリを利用すると便利です。携帯の有料オプションに加入し続けていないか、見ていないのに動画配信サービスに加入し続けていないか、スマホアプリに課金しすぎていないか、など自分の支出を振り返ってみましょう。
また、お金があるとついつい使ってしまうという場合は普段利用している口座とは別の場所に自動的に月の貯金額が隔離されるような仕組みを作ってみましょう。会社の財形貯蓄や積立保険、銀行の積立定期預金などを利用するとよいでしょう。いずれも普段使う口座とは別の場所に自動的にお金が貯まっていくので、貯金が苦手な人でもお金を貯めやすいです。
貯蓄がないと大きなケガや病気をした時、老後で収入が少なくなった時などに生活が非常に苦しくなってしまいます。今後の生活の安定のためにもまずは手取りの10%を貯蓄に回してみて、余裕があるようならば20%、30%と貯蓄の割合を増やしていきましょう。

-
著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。
\【知れば納得 SBI証券のNISA】/
100円から始められるから投資初心者におすすめ!