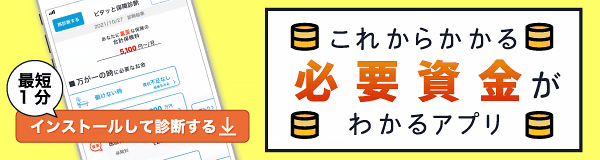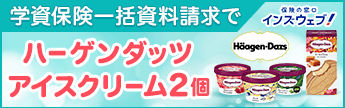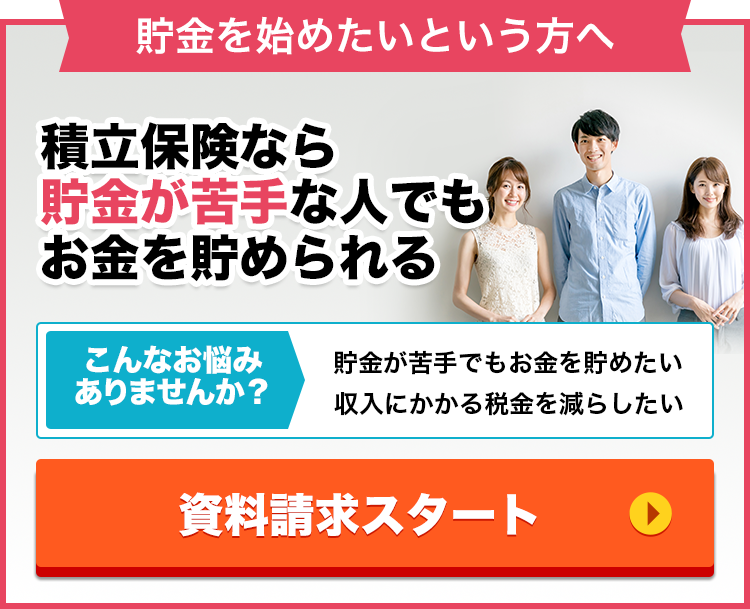20代だと社会人となったばかりで収入も少なく、なかなか貯金もできないという人も多いのではないでしょうか。しかし、今後の結婚や子供の教育資金、住宅購入費用などを考えると、今から少しずつでも貯めていくのが賢明です。20代の場合、どれくらいの貯金があるものなのでしょうか。また、お金を貯めるにはどのようにすればよいのでしょうか。
目次
どんな保険が必要か、いくらの保障が必要なのか分からない方へ
簡単な質問に答えるだけで、あなたに必要な備えと保障金額がすぐにわかります。
最短1分、無料でご利用可能ですので、ぜひお試しください!
\自分に必要な保障がわかる!/
20代の貯蓄額の平均・中央値
20代はどれくらいの資産を持っているのか、平均値と中央値をJ-FLEC「家計の金融行動に関する世論調査」より紹介します。なお、貯金だけではなく株式や保険なども含まれていますのでご注意ください。
中央値とは
中央値というのは、データを小さい順に並べたときに中央に位置する値のことです。例えば、「1、2、3、4、105」という5つの数字の場合、小さい方から3番目の3が中央値です。なお、この5つの数字の平均値は23です。105という極端な数値に引っ張られて直感的な「真ん中」からずれてしまいます。
単身世帯の場合
| 金融資産保有額 | 割合 |
|---|---|
| 平均 | 161万円 |
| 中央値 | 15万円 |
| 非保有 | 36.6% |
| 100万円未満 | 26.3% |
| 100~200万円未満 | 9.5% |
| 200~300万円未満 | 4.9% |
| 300~400万円未満 | 4.8% |
| 400~500万円未満 | 2.4% |
| 500~700万円未満 | 4.6% |
| 700~1000万円未満 | 4.0% |
| 1000~1500万円未満 | 2.4% |
| 1500~2000万円未満 | 0.4% |
| 2000~3000万円未満 | 0.4% |
| 3000万円以上 | 0% |
| 無回答 | 3.8% |
出典:J-FLEC「家計の金融行動に関する世論調査 2024年(単身世帯調査)」
20代の単身世帯の場合、貯蓄額の平均は161万円、中央値は15万円という結果でした。貯蓄がないか、あっても100万円未満という割合は合わせて62.9%です。20代ではなかなかお金を貯めるのが難しいようです。
年収別貯蓄額
貯蓄のしやすさというのは年収によっても変わってくるでしょう。そこで、同じく「家計の金融行動に関する世論調査 2024年(単身世帯調査)」より、年収別の金融資産保有額を紹介します。
| 年収 | 対象数 | 平均 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 収入なし | 61 | 18万円 | 0万円 |
| 300万円未満 | 267 | 98万円 | 10万円 |
| 300~500万円未満 | 165 | 233万円 | 60万円 |
| 500~750万円未満 | 44 | 430万円 | 310万円 |
| 750~1000万円未満 | 5 | 132万円 | 0万円 |
| 1000~1200万円未満 | 3 | 495万円 | 445万円 |
| 1200万円以上 | 2 | 475万円 | 475万円 |
出典:J-FLEC「家計の金融行動に関する世論調査 2024年(単身世帯調査)」
年収750万円以上は回答者数が少なくあまり参考になりませんが、年収が多いほど貯蓄額が増える傾向が見て取れます。
二人以上世帯の場合
続いて、二人以上世帯のデータも紹介します。世帯主の年齢が20歳代のデータなので、親と同居しているのではなく20代で結婚している人などのデータです。単身世帯と比べて回答数がかなり少ないので参考程度にしてください。
| 金融資産保有額 | 割合 |
|---|---|
| 平均 | 382万円 |
| 中央値 | 84万円 |
| 非保有 | 22.8% |
| 100万円未満 | 23.4% |
| 100~200万円未満 | 11.1% |
| 200~300万円未満 | 5.3% |
| 300~400万円未満 | 4.1% |
| 400~500万円未満 | 6.4% |
| 500~700万円未満 | 5.8% |
| 700~1000万円未満 | 4.1% |
| 1000~1500万円未満 | 5.8% |
| 1500~2000万円未満 | 0.6% |
| 2000~3000万円未満 | 0% |
| 3000万円以上 | 2.3% |
| 無回答 | 8.2% |
出典:J-FLEC「家計の金融行動に関する世論調査 2024年(二人以上世帯調査)」
年収別貯蓄額
| 年収 | 対象数 | 平均 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 収入なし | 9 | 71万円 | 8万円 |
| 300万円未満 | 38 | 218万円 | 20万円 |
| 300~500万円未満 | 47 | 354万円 | 92万円 |
| 500~750万円未満 | 46 | 354万円 | 210万円 |
| 750~1000万円未満 | 15 | 269万円 | 50万円 |
| 1000~1200万円未満 | 10 | 850万円 | 495万円 |
| 1200万円以上 | 6 | 1670万円 | 623万円 |
出典:J-FLEC「家計の金融行動に関する世論調査 2024年(二人以上世帯調査)」
20代で年収1000~1200万円未満の6人の内訳をみると、金融資産非保有が2人、貯蓄額が400~500万円未満という人が3人、700~1000万円未満が1人、1000~1500万円未満が2人、3000万円以上が1人という結果になっています。
お金を貯めるには「先取り貯金」の考え方が重要!
調査結果を見る限り、20代ではあまり貯金できている人はいなさそうです。しかし、そこで安心して貯金しなくてもいいというわけではありません。これからお金がかかる様々なライフイベントが控えているので、将来のことを考えて少しでも貯蓄を始めるべきでしょう。
それでも、「貯金が苦手で貯めようと思っても貯められない…」という人もいるでしょう。そういう人がお金を貯めるには「先取り貯金」の考え方を徹底することが大切です。
先取り貯金というのは、収入から先に貯金分を引き、残った金額で生活するという貯金法です。つまり、「収入-貯金=支出」という考え方です。生活費の余った分を貯金する「収入-支出=貯金」では、ついつい使いすぎてしまってなかなかお金を貯めることはできません。給料が入ったら先に貯金分を別の場所に移してしまいましょう。
-

-
貯金の基本は先取り貯金!失敗しない方法は?
将来のためにお金を貯めたいけどなかなか貯まらない…とお悩みの方はいませんか?そんな方におすすめなのが先取り貯金です。しかし、先取り貯金を始めてみても思うよう貯ま ...続きを見る
手取りからどれくらい貯金に回すのがいい?
先取り貯金をするとして、毎月の貯金額はどれくらいが目安となるのでしょうか。J-FLEC「家計の金融行動に関する世論調査 2024年」によると、年間手取り収入(臨時収入を含む)からの貯蓄割合は、20歳代の単身世帯は平均30%、二人以上世帯は平均33%となっています。
| 単身世帯 | 二人以上世帯 | |
|---|---|---|
| 対象数 | 347 | 132 |
| 5%未満 | 4.3% | 3.0% |
| 5~10%未満 | 3.5% | 6.1% |
| 10~15%未満 | 9.5% | 7.6% |
| 15~20%未満 | 1.7% | 3.0% |
| 20~25%未満 | 5.5% | 8.3% |
| 25~30%未満 | 0.6% | 0% |
| 30~35%未満 | 4.0% | 8.3% |
| 35%以上 | 14.1% | 22.0% |
| 貯蓄しなかった | 56.8% | 41.7% |
| 平均 | 30% | 33% |
出典:J-FLEC「家計の金融行動に関する世論調査 2024年」
生活にあまり余裕がない場合には手取りの10%前後を目安に、生活に余裕がある場合には手取りの20%や30%といった金額を貯金するとよいでしょう。
ある程度貯まったら貯金以外の手段も考えよう
貯金が全くない場合にはまずは給料の3か月分などある程度の額の貯金をするべきですが、貯金にはほぼ利息が付かないのである程度の貯金が貯まったら貯金以外の方法で貯めることも検討しましょう。ここでは貯金以外の手段として積立保険とつみたてNISAを紹介します。
積立保険
積立保険とは、そういう名前の保険があるのではなく、満期保険金や解約返戻金などで貯蓄性のある保険のことです。契約者が払い込んだ保険料は保険本来の目的である保障のための部分と貯蓄のための部分に分けられます。満期時や解約時に戻ってくるのは、貯蓄のために積み立てられ、運用されたお金です。
積立保険は毎月保険料として口座から自動的に引き落とされていくので意志が弱い人でもお金を貯めていきやすいです。また、長引く低金利の影響で積立保険の利率も下がってしまっていますが、貯金よりも高い利率となる商品も多くあります。ただし、注意点として、早期解約してしまうと支払った保険料の総額よりも少ない金額しか戻ってこないことが多いです。契約時にきちんと最後まで支払えるのかよく検討するのがよいでしょう。
-

-
積立保険で貯金するのはあり?なし?
保険の中には保障のほかに貯蓄性があることを売りにしているものがあります。そうした貯蓄性の積立保険で貯金するのは「あり」なのでしょうか。それとも「なし」なのでしょ ...続きを見る
つみたてNISA
つみたてNISAというのは特定の金融商品を指すものではなく、年間40万円までの非課税投資枠で購入した投資信託等から得られた譲渡益、分配金・配当金の税金が非課税となる制度です。通常は利益に約20%の税金がかかりますが、それが非課税となります。
つみたてNISAでは、基本的に毎月コツコツと投資信託の購入を続けることになります。そして、これを長期間続けることによって貯金や積立保険では得られない大きな利益を期待することができます。一方で、投資ですのでリスクはつきものです。お金が必要となったタイミングでリーマンショックのようなことが起こって大きくマイナスとなることもありえます。そのため、必ず余裕資金で投資を行うようにする必要があります。
まとめ
20代はまだまだ収入も少ないせいか、金融資産保有額の平均や中央値は非常に小さくなっています。しかし、だからと言って貯金しなくてもよいというわけではありません。「収入-貯金=支出」という先取り貯金の考え方で将来に向けて着実にお金を貯めていきましょう。そして、貯金だけでなく積立保険やつみたてNISAなど他の手段にも目を向けられるとよいでしょう。

-
著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。
\【知れば納得 SBI証券のNISA】/
100円から始められるから投資初心者におすすめ!