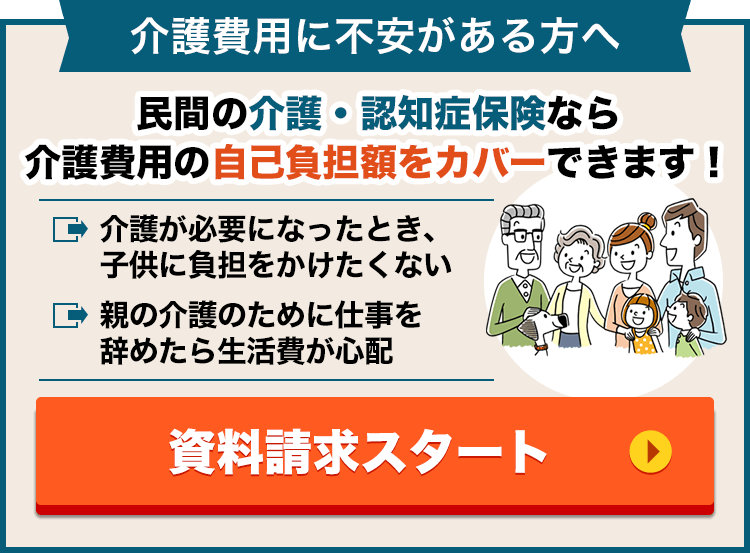高齢化の進展により、認知症は身近な問題となってきています。そうした状況から、民間の保険で認知症保険というものが登場してきています。名前の通り認知症に備える保険ですが、具体的にはどのような保険なのでしょうか。また、デメリットはないのでしょうか。
目次
どんな保険が必要か、いくらの保障が必要なのか分からない方へ
簡単な質問に答えるだけで、あなたに必要な備えと保障金額がすぐにわかります。
最短1分、無料でご利用可能ですので、ぜひお試しください!
\自分に必要な保障がわかる!/
認知症保険とは?
認知症保険とは、認知症と診断されて保険会社が定める所定の状態に該当した場合に保険金の給付を受けられる保険です。認知症保険と呼ばれる保険はいくつか登場していますが、認知症保険が登場してきてからあまり年数が経っておらず、給付金が支払われる条件など各社によって違いがある状況です。
認知症保険が登場してきた要因の一つに、高齢化が進んで認知症が身近な問題となってきたことがあげられます。2022年の時点で65歳以上の認知症の人は約443万人と推計されており、2030年には約523万人、2060年には約645万人が認知症となることが推計されています。認知症の介護には多くの費用がかかります。その経済負担に備える必要性から認知症保険が登場してきたのです。
※出典:公益財団法人生命保険文化センター 認知症患者はどのくらい?
認知症にはいくらかかる?
認知症にかかる費用について、慶応大学と厚生労働科学研究の共同研究グループが推計を発表しています。その推計によると、1人あたりの医療費・介護費は以下の通りです。
- 入院医療費:34万4300円/月、外来医療費:3万9600円/月
- 在宅介護費:219万円/年、施設介護費:353万円/年
なお、この費用がすべて自己負担となるわけではありません。所得水準にもよりますが、医療費は70歳以上75歳未満の高齢者は2割負担、75歳以上の後期高齢者は1割負担となります。また、公的介護保険適用となる介護サービスも1~3割の負担となります。
また、インフォーマルケアコストについても推計がなされています。インフォーマルケアとは家族等が無償で行う介護のことです。認知症の介護者を対象とした調査票による調査でインフォーマルケア時間を推計し、それに市場で購入していたら発生していた代替費用や介護の時間を労働に充てていたら得られるであろう賃金を組み合わせて計算した介護単価をかけてインフォーマルケアコストを推計しています。
この結果、インフォーマルケアにかかる時間は要介護者1人あたり24.97時間/週、インフォーマルケアコストは要介護者1人あたり382万円/年と推計されています。
将来の介護に関するお金の悩みを保険で解決!
-

-
2025年には高齢者の5人に1人は認知症に…医療費・介護費はいくらかかる?
近年、高齢化の進展とともに認知症の高齢者の数が増えていて、今後も増加していくことが予想されています。2000万円という数字が独り歩きしてしまった感のある、いわゆ ...続きを見る
認知症保険は必要?
2022年の時点で約443万人が認知症を発症していると推計されています。現在の日本は少子高齢化が進んでおり、人口に占める高齢者の割合は増加を続けているという現状があります。
認知症は介護が必要となる原因の1位であり、平均寿命も延びていることからも自分が将来、認知症になり介護が必要となってしまうリスクは誰にでもあります。もちろん、認知症にならないような予防を心がけて生活する事が一番大切ですが、認知症を発症してしまい介護が必要な状態となるかもしれない備えについても考えておくことは重要です。
認知症になってしまった時の経済的な負担は上項で紹介しましたが、介護に係る自己負担となってしまう費用は家族に負担をかけるという心配があります。そのような経済的負担をカバーするために認知症保険で備えておくという人も増えています。
認知症保険の加入率
生命保険文化センターの2024(令和6)年度「生命保険に関する全国実態調査」によると、民間の介護保険・介護特約の世帯加入率は20.1%です。世帯員別にみると、世帯主は16.8%、配偶者は11.0%となっています。同調査は3年ごとに行われており、前回の調査(2021年)と比べて3ポイントほど上昇しています。
| 世帯 | 世帯主 | 配偶者 | |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 20.1% | 16.8% | 11.0% |
| 2021年 | 16.7% | 13.6% | 8.5% |
| 2018年 | 14.1% | 10.5% | 7.8% |
| 2015年 | 15.3% | 11.8% | 7.9% |
| 2012年 | 14.2% | 10.8% | 7.6% |
- ※民保(かんぽ生命を除く)に加入している世帯が対象
- ※寝たきりや認知症によって介護が必要な状態になり、その状態が一定の期間継続したときに、一時金や年金などが受け取れる生命保険、あるいは特約が付加された生命保険であり、損害保険は含まれない
世帯主年齢別加入率
つづいて、同調査より世帯主年齢別の加入率を紹介します。
| 世帯主年齢 | サンプルサイズ | 世帯 | 世帯主 | 配偶者 |
|---|---|---|---|---|
| 29歳以下 | 64 | 15.6% | 12.5% | 10.9% |
| 30~34歳 | 127 | 21.3% | 20.5% | 8.7% |
| 35~39歳 | 285 | 21.4% | 20.0% | 12.3% |
| 40~44歳 | 299 | 17.1% | 15.7% | 7.4% |
| 45~49歳 | 332 | 18.1% | 16.9% | 10.2% |
| 50~54歳 | 384 | 21.6% | 20.3% | 12.2% |
| 55~59歳 | 318 | 26.4% | 21.7% | 14.8% |
| 60~64歳 | 320 | 26.6% | 20.9% | 15.0% |
| 65~69歳 | 297 | 21.2% | 16.2% | 12.1% |
| 70~74歳 | 316 | 16.1% | 11.1% | 8.2% |
| 75~79歳 | 202 | 13.9% | 7.9% | 9.4% |
出典:生命保険文化センター「2024(令和6)年度『生命保険に関する全国実態調査』」
介護とは縁が薄めの29歳以下で若干低く、また、現役引退後と思われる70歳以上では加入率が低くなっています。加入率が最も高いのは60代前半で、介護が身近な話題となってきたことや介護のために保険料を支払う金銭的余裕があることが大きいのではないかと思います。
将来の介護に関するお金の悩みを保険で解決!
世帯年収別加入率
世帯年収別のデータについても紹介します。
| 世帯年収 | サンプルサイズ | 世帯 | 世帯主 | 配偶者 |
|---|---|---|---|---|
| 200万円未満 | 125 | 14.4% | 12.0% | 2.4% |
| 200~300万円未満 | 216 | 14.8% | 12.5% | 3.7% |
| 300~400万円未満 | 323 | 17.3% | 12.7% | 10.2% |
| 400~500万円未満 | 353 | 19.3% | 15.3% | 11.0% |
| 500~600万円未満 | 380 | 18.7% | 16.1% | 8.7% |
| 600~700万円未満 | 292 | 20.2% | 17.8% | 12.3% |
| 700~1000万円未満 | 761 | 23.9% | 20.4% | 13.7% |
| 1000万円以上 | 472 | 24.2% | 20.1% | 15.5% |
| 不明 | 163 | 12.9% | 10.4% | 6.1% |
出典:生命保険文化センター「2024(令和6)年度『生命保険に関する全国実態調査』」
やはり傾向として、世帯年収が低いほど加入率も低く、世帯年収が高いほど加入率も高くなるようです。介護保険・介護特約のために保険料を支払うだけの余裕が加入率に影響を与えているのでしょう。
認知症保険のデメリットは何?
多くの費用がかかる認知症に備えられる認知症保険ですが、メリットだけでなくデメリットもあります。どのようなデメリットがあるのか紹介します。
認知症の診断後すぐに給付金を受け取れない
保険商品によりますが、医師により認知症という診断確定を受けただけでは給付金を受け取れないことがあります。要介護1以上の認定がされている必要があったり、診断を受けてその状態が180日間継続する必要があったりします。要介護認定を受けるにしても180日間待つにしても時間がかかります。認知症の診断を受けてすぐに給付金を受け取れるわけではないので注意が必要です。
要介護認定については申請してから認定まで原則30日以内とされていますが、訪問調査や医師のスケジュールの都合や申請が多くある場合の事務手続きの混雑などで30日以上かかることも多くあるようです。
すべての「認知症」で給付を受けられるわけではない
給付対象となる認知症は約款等で定められていて、そこから外れるものについては給付金を受けられません。例えば、単なる加齢による物忘れはもちろんとしてアルコールを原因とする認知症なども給付対象となっていない場合があります。また、認知症の中核症状である見当識障害が発生していることを給付の条件に含む場合もあります。見当識障害とは、時間・場所・人が分からなくなる状態です。夜なのに朝食の催促をする、散歩に出かけて家に戻れない、友人や親戚が認識できないなどの症状です。
世間一般では様々な原因のものをひっくるめて「認知症」と呼んでいますが、契約前に給付の条件をよく確認する必要があります。
加入していることを忘れてしまうおそれがある
認知症保険に加入していても、加入した本人が認知症になって加入したことを忘れてしまう可能性があります。その時に家族が誰も認知症保険に加入していることを知らないと給付金をもらい損ねてしまいます。自身の認知症に備えて認知症保険に加入した場合はその事実を家族などに伝えておく必要があります。
解約返戻金がない
ほとんどの認知症保険は掛け捨て型で解約返戻金がありません。途中で解約してしまうとそれ以降の保障がなくなり、それまで払った保険料も戻ってきません。保険料はいつまで払い続けるのか、終身払いなどの場合は年金生活となっても支払い続けられるかなどを契約前にしっかりと確認し、保険料が払えなくて解約するというようなことにはならないように注意が必要です。
損害賠償リスクに備えるには?
認知症で備える必要がある費用は医療費や介護費だけではありません。誰かにケガをさせてしまったり他の人のものを壊してしまったりした場合の損害賠償も考える必要があります。介護施設の職員や他の利用者に暴力をふるってケガをさせてしまうというのは十分考えられることだと思います。
また、電車などを停めてしまうと多額の賠償を負う可能性もあります。例えば、愛知県大府市の事例では、認知症の男性が線路内に立ち入り電車にはねられて亡くなってしまったのですが、その遺族に電車遅延の損害賠償請求が起こされました。この事例では結果的に最高裁で遺族側が逆転勝訴しましたが、その理由は死亡した男性の妻も介護が必要な状態で、子も遠方に住んでいて監督義務を負わないと判断されたからです。監督義務があると判断されていれば、一審・二審通りに高額な賠償責任を負っていた可能性もあります。
こうした損害賠償責任に備えるのには個人賠償責任保険が有効です。個人賠償責任保険は火災保険や自動車保険、クレジットカードなどの特約で加入することができます。個人賠償責任保険が活用できる場面は広く、自転車で歩行者にケガをさせてしまった場合や飼い犬が人を噛んでケガをさせてしまった場合、店舗でガラス製品を落として壊してしまった場合など様々な場合に利用できます。認知症に備えるため以外でも検討する価値はあるでしょう。
▼一括資料請求で保険会社を比較するワケ
▼一括資料請求で保険会社を比較するワケ
- ネットで簡単に資料請求!時間がない方にピッタリ
- 各社保障が違う商品から自分に合った保険を選べる
- 大切な資料を手元に残せる
まとめ
認知症保険では認知症と診断されて所定の状態に該当した場合に保険金が支払われます。高齢化が進み、認知症が身近になる中で認知症保険は魅力を増していますが、デメリットも存在しています。特に、給付条件や払込期間、保険料などは事前によく確認しておく必要があります。しかし、認知症には多くの費用がかかるのは事実です。その費用負担に不安があるのであれば認知症保険を検討してみてはいかがでしょうか。

-
著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。