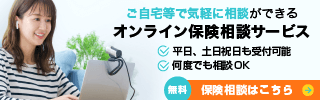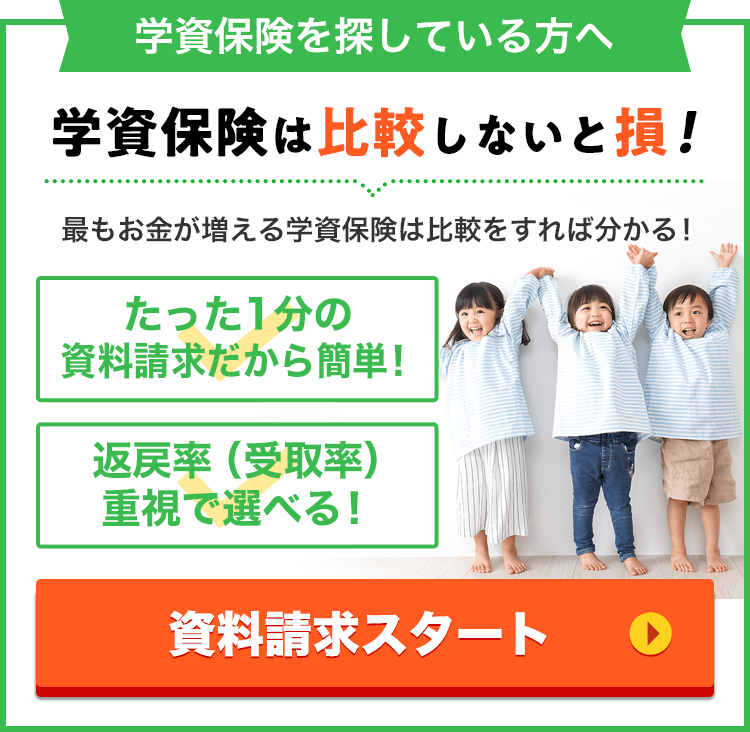子どもが生まれると何かとお金がかかるもの。大学を卒業するまでにかかる子育て費用は約3,000万円といわれています。申請すればもらえる手当や助成制度を活用して、少しでも負担額を減らしたいものですよね。出産や子育てに関する『もらえるお金』について紹介します。
進路別教育費シミュレーション
目次
妊娠時にもらえるお金

妊婦健康診査費用の助成
妊娠中の定期検診(妊婦健康診査)にかかる費用は全額自己負担となりますが、全国の市区町村では検査費用の一部を助成する制度があります。お住まいの市区町村で妊娠の届け出を行うと、妊婦健康診査の受診券が発行され公費負担で妊産婦健康診査を受診できます。こども家庭庁の調査によると、公費負担額の全国平均は約10.9万円になります。
妊婦のための支援給付
2025年4月より全国の市区町村で始まった制度ですが、「妊婦のための支援給付」では妊娠後2回に分けて計10万円が受け取れます。給付と面談がセットで実施され、給付額は妊娠認定時に5万円、出産予定日8週間前の給付では妊娠している赤ちゃんの人数×5万円となります。なお、自治体によっては現金給付ではなくクーポンや電子マネーを支給するところもあるようです。
出産時にもらえるお金

出産育児一時金
妊娠4ヵ月(85日)以上の方が出産した場合、一児につき50万円(妊娠週数22週未満の出産の場合や産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は48.8万円)の出産育児一時金が支給されます。一時金は加入する健康保険から直接医療機関等へ支払われるため、医療機関等の窓口で出産にかかった高額な費用を支払う必要がありません。
出産手当金
産休中はほとんどの会社で給料が出ませんが、健康保険に加入している場合は出産手当金が支給されます。出産日以前42日~出産の翌日以降56日目までの範囲内で会社を休んだ期間が対象です。収入によって支給額が異なりますが、過去12ヵ月の給料(標準報酬月額)を基準とした日給の3分の2に相当する額になります。
医療費が高額になったら?
妊娠中に切迫早産等で入院した場合や、出産時に帝王切開等の手術が必要な場合は医療費が高額になる可能性があります。そんな時に利用できる制度を2つ紹介します。
高額療養費制度
1カ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合、高額療養費制度を申請すれば超過分の金額が払い戻されます。
医療費控除
一年でかかった医療費が10万円を超えた場合(総所得額が200万円未満の人は総所得金額の5%を超えた場合)は確定申告をすると医療費控除を受けられます。不妊治療や妊婦健診の費用、通院費用なども対象になり、家族の医療費も含まれます。
子育てでもらえるお金

児童手当
高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人に手当がもらえます。1カ月あたり15,000円あるいは10,000円(第3子以降は30,000円)が支給されます。
| 支給対象児童 | 一人あたり月額 |
|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 (第3子以降は30,000円) |
| 3歳以上 高校生年代まで |
10,000円 (第3子以降は30,000円) |
育児休業給付金
雇用保険に加入している場合は、1歳未満の子どもを養育する目的で育児休業を取得した際に給付を受けられます。子どもが生まれてから180日までは月給の67%が支給され、181日以降は月給の50%が給付されます。なお、支給される金額には上限があります。
| 給付率 | 支給上限額 |
|---|---|
| 67% | 月額323,811円 |
| 50% | 月額241,650円 |
育児休業は子どもが1歳になるまでの間なら2回に分けて取得できます。育児休業給付金も受給できますので、夫婦交代で育休を取ることも可能です。
なお、雇用保険に加入していても下記に該当するともらえない可能性があるため注意しましょう。
- 妊娠中に勤務先を退職する場合
- 育児休業開始の時点で育休後に会社を辞める予定がある人
- 育休を取らずに仕事に復帰する人
出生時育児休業給付金(産後パパ育休)
産後パパ育休は子どもが生まれてから8週間以内に28日間まで、2回に分けて取得できる休業です。1歳までの育児休業とは別に取得でき、賃金日額の67%が休業日数に乗じて支給されます。労使協定を締結している場合、労働者が合意した範囲で休業中に働くこともできます。
| 給付率 | 支給上限額 |
|---|---|
| 67% | 日額16,110円 |
出生後休業支援給付金
2025年4月以降に始まった制度ですが、子どもの出生後8週間以内に育児休業を取得すると出生後休業支援給付金が最大28日間支給されます。賃金日額の13%が休業日数に乗じて支払われます。育児休業給付金(67%)と出生後休業支援給付金(13%)を合わせて受け取れるため、給与の80%が給付されることになります。こちらも支給される金額に上限があります。
| 給付率 | 支給上限額 |
|---|---|
| 13% | 日額16,110円 |
育児時短就業給付金
育児時短就業給付金は2025年4月に始まった制度です。雇用保険に加入している場合、2歳未満の子どもを養育するために時短勤務をすると、時短勤務中の賃金の10%が支給されます。フレックスタイム制やシフト制で勤務時間が短縮となっても給付を受けられます。支給される上限額は以下の通りです。
| 給付率 | 支給上限額 |
|---|---|
|
10% |
月額483,300円 |
なお、時短勤務によって給料が減少していない場合や、月給が限度額以上の場合は支給されないため注意しましょう。
会社の福利厚生
企業によっては仕事と育児の両立を支援するために、福利厚生やお祝い金制度を用意しているケースもあります。
- 会員制福利厚生サービスでベビー用品のレンタル費用や購入価格が割引
- 出産祝い金制度
- 職場復帰時の奨励金制度
- 専用の保育所を設置
ひとり親家庭への公的支援
ひとり親家庭の場合、親が働きながら子育てや家事も全てこなさなければなりません。もらえるお金だけでなく、助成制度や給付金、減免・割引制度など、利用できる公的支援の存在を知っておくことが大切です。
児童扶養手当
死亡や離婚等により父または母がいない児童や、父または母が一定以上の障害の状態にある児童が育成される家庭の養育者に支給されます。所得制限があり、所得によっては一部支給となります。
| 全部支給 | 一部支給 | |
|---|---|---|
| 児童1人目 | 46,690円 | 11,010円~ 46,680円 |
| 加算額(児童2人目以降1人につき) | 11,030円 | 5,520円~ 11,020円 |
児童育成手当
児童育成手当は東京都独自の制度になります。死亡や離婚等により父または母がいない、あるいは父または母に重度の障害がある児童を養育している人を対象に、児童一人につき月額13,500円が支給されます。受給者の所得制限があります。
割引・減免制度
児童扶養手当を受けている世帯の場合、公共料金や公共交通機関の割引や減免を利用することができます。内容は自治体によって異なりますので、お住まいの市区町村にどのような制度があるのか確認してみましょう。一例としては以下のようなものがあります。
- 上下水道料金の割引
- JR定期乗車券の割引
- 公共交通機関の無料乗車券交付
ひとり親家庭休養ホーム事業
ひとり親家庭で宿泊施設や日帰り施設を利用する時に料金が助成されます。利用できる施設は自治体によって異なりますが、ディズニーランドやユニバーサル・スタジオ・ジャパンなどが対象になっている自治体もあります。回数制限や助成額に上限があることが多いものの、旅行やレジャーにかかる費用を抑えることができるでしょう。
障がいのある子どもへの公的支援
障がいのあるお子さんを育てる家庭に、国の制度として特別児童扶養手当と障害児福祉手当があります。お住まいの自治体によって独自の制度が設けられていることもありますので、詳しくは都道府県や市区町村のサイトを確認してください。
特別児童扶養手当
精神または身体に障害をもつ20歳未満の子どもを養育している父母に支給されます。障害の程度によって支給額が異なり、所得制限があります。申請には身体障害者手帳や愛の手帳、医師の診断書等の提出が必要になります。
| 支給月額 | |
|---|---|
| 1級 | 56,800円 |
| 2級 | 37,830円 |
障害児福祉手当
重度障害をもち日常生活で常時の介護を必要とする20歳未満の子どもを養育している父母に、月額16,100円が支給されます。
免除になるお金
もらえるお金だけでなく、支払いが免除されるお金もあります。
子ども医療費助成制度
子どもの医療費の自己負担額を自治体が負担してくれる制度です。都道府県では通院が「就学前まで」、市区町村では「18歳年度末まで」とする地域が多く、所得によって全額負担~一部負担になる地域もあります。
社会保険料免除
産休中と育休中は、被保険者本人と企業負担分の社会保険料が免除になります。
育休後の社会保険料の特例
育休から復帰して3ヶ月間以上時短勤務で働く場合、社会保険料の標準報酬月額を時短勤務で下がってしまった給料をベースに引き下げてもらえます。社会保険料が下がった分手取りは増えるというメリットがありますが、将来の年金額の算定額が下がってしまう他、次の子どもの妊娠を予定している場合は出産手当金の金額も下がってしまう可能性があるといったデメリットもあります。
教育費の公的支援

幼児教育・保育の無償化
幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する場合、3~5歳までの全ての子どもの保育料が無償化されます。住民税非課税世帯の場合は0~2歳の保育料が無料となります。給食費や延長保育代などは自己負担となります。
高等学校等就学支援金
2025年4月より、公立高校の授業料は完全無償化となりました。私立高校に進学する場合は最大396,000円が支給されますが所得制限があります。家族構成や収入によっては公立高校と同じ支給額(118,800円)となります。
基本的に入学後に申請するため、入学前に必要になる授業料は一旦自己負担しなければなりません。特に私立高校は高額になるケースが多いため、ある程度まとまった資金を用意しておきましょう。
高校生等奨学給付金
授業料は無償化となっていますが、教科書代や制服代などの費用はかかります。低所得者世帯が対象となる「高校生等奨学給付金」では授業料以外の教育費についても給付金を受けられます。お住まいの都道府県によって給付条件や給付額は異なり、入学後に高校経由で申請することもできるようです。
高等教育の修学支援制度
大学や短大、専門学校に進学する場合は授業料等の減免や給付型奨学金が受けられます。制度の利用には所得制限や学習意欲などの条件があります。
2025年からは3人以上の子どもがいる多子世帯は所得制限なしで無償化対象になりました。しかし、第1子が就職して扶養から外れ扶養する子どもが2人になった場合、第2子以降は無償化対象外となるため注意が必要です。
教育費は計画的に準備しよう
出産前や育児中といった働けない期間は、会社の福利厚生制度や公的支援制度を活用して収入源を少しでもカバーすると良いでしょう。
子どもにかかる教育費への公的支援が増えてきたとはいえ、教育費がゼロになるわけではありません。授業料以外の費用(教科書代や学用品代、修学旅行代等)は自己負担となることが多いです。そこで、子どもが小さいうちから教育資金を用意していきましょう。我が子の将来のために計画的に準備したい方は、学資保険を活用して積み立てていきませんか?