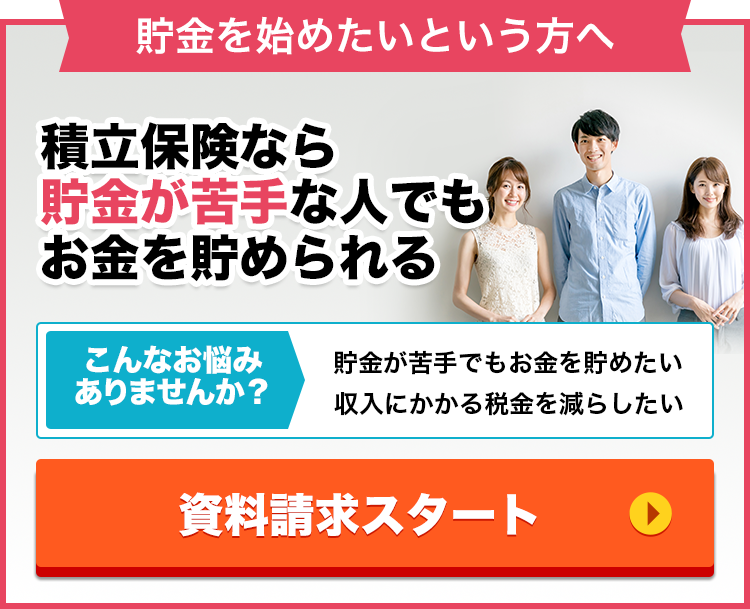日本では超低金利の状況が続き、銀行に貯金しているだけではお金は増えないということは常識となっています。「貯蓄から投資へ」というスローガンも掲げられていますが、実態としてどれくらいの割合で保有資産を投資へと回しているのでしょうか。
どんな保険が必要か、いくらの保障が必要なのか分からない方へ
簡単な質問に答えるだけで、あなたに必要な備えと保障金額がすぐにわかります。
最短1分、無料でご利用可能ですので、ぜひお試しください!
\自分に必要な保障がわかる!/
種類別金融商品保有額は?
J-FLECの「家計の金融行動に関する世論調査 2024年」から、単身世帯と二人以上世帯に分けて金融資産保有世帯の種類別金融商品保有額とそこから計算した種類別金融商品保有割合を紹介します。
単身世帯
種類別金融商品保有額(単位:万円)
| 金融資産保有額 | 預貯金 | 金銭信託・貸付信託 | 生命保険 | 損害保険 | 個人年金保険 | 有価証券 | 財形貯蓄 | その他金融商品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 1,497 | 547 | 9 | 129 | 13 | 87 | 678 | 8 | 25 |
| 20歳代 | 260 | 147 | 4 | 8 | 1 | 4 | 92 | 2 | 3 |
| 30歳代 | 700 | 305 | 2 | 32 | 4 | 32 | 304 | 12 | 9 |
| 40歳代 | 1342 | 503 | 17 | 45 | 2 | 50 | 698 | 6 | 20 |
| 50歳代 | 1,859 | 717 | 4 | 156 | 13 | 144 | 740 | 30 | 55 |
| 60歳代 | 2,363 | 775 | 8 | 237 | 30 | 193 | 1062 | 5 | 52 |
※有価証券は債券、株式、投資信託の合計
出典:J-FLEC「家計の金融行動に関する世論調査 2024年(単身世帯調査)」
種類別金融商品保有割合
| 金融資産保有額 | 預貯金 | 金銭信託・貸付信託 | 生命保険 | 損害保険 | 個人年金保険 | 有価証券 | 財形貯蓄 | その他金融商品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 100% | 37% | 1% | 9% | 1% | 6% | 45% | 1% | 2% |
| 20歳代 | 100% | 57% | 2% | 3% | 0% | 2% | 35% | 1% | 1% |
| 30歳代 | 100% | 44% | 0% | 5% | 1% | 5% | 43% | 2% | 1% |
| 40歳代 | 100% | 37% | 1% | 3% | 0% | 4% | 52% | 0% | 1% |
| 50歳代 | 100% | 39% | 0% | 8% | 1% | 8% | 40% | 2% | 3% |
| 60歳代 | 100% | 33% | 0% | 10% | 1% | 8% | 45% | 0% | 2% |
※有価証券は債券、株式、投資信託の合計
※小数点以下第1位で四捨五入しているため、合計が100%にならない場合がある
出典:J-FLEC「家計の金融行動に関する世論調査 2024年(単身世帯調査)」より筆者計算
二人以上世帯
種類別金融商品保有額(単位:万円)
| 金融資産保有額 | 預貯金 | 金銭信託・貸付信託 | 生命保険 | 損害保険 | 個人年金保険 | 有価証券 | 財形貯蓄 | その他金融商品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 1,833 | 776 | 27 | 206 | 24 | 105 | 641 | 24 | 30 |
| 20歳代 | 508 | 175 | 35 | 28 | 7 | 10 | 236 | 9 | 7 |
| 30歳代 | 909 | 468 | 12 | 65 | 10 | 32 | 294 | 18 | 9 |
| 40歳代 | 1,293 | 551 | 26 | 155 | 19 | 67 | 416 | 37 | 22 |
| 50歳代 | 1,677 | 671 | 30 | 224 | 21 | 136 | 524 | 42 | 28 |
| 60歳代 | 2,581 | 1,030 | 39 | 258 | 34 | 187 | 964 | 21 | 49 |
| 70歳以上 | 2,450 | 1087 | 19 | 293 | 32 | 89 | 889 | 7 | 35 |
※有価証券は債券、株式、投資信託の合計
出典:J-FLEC「家計の金融行動に関する世論調査 2024年(二人以上世帯調査)」
種類別金融商品保有割合
| 金融資産保有額 | 預貯金 | 金銭信託・貸付信託 | 生命保険 | 損害保険 | 個人年金保険 | 有価証券 | 財形貯蓄 | その他金融商品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 100% | 42% | 1% | 11% | 1% | 6% | 35% | 1% | 2% |
| 20歳代 | 100% | 34% | 7% | 6% | 1% | 2% | 46% | 2% | 1% |
| 30歳代 | 100% | 51% | 1% | 7% | 1% | 4% | 32% | 2% | 1% |
| 40歳代 | 100% | 43% | 2% | 12% | 1% | 5% | 32% | 3% | 2% |
| 50歳代 | 100% | 40% | 2% | 13% | 1% | 8% | 31% | 3% | 2% |
| 60歳代 | 100% | 40% | 2% | 10% | 1% | 7% | 37% | 1% | 2% |
| 70歳以上 | 100% | 44% | 1% | 12% | 1% | 4% | 36% | 0% | 1% |
※有価証券は債券、株式、投資信託の合計
※小数点以下第1位で四捨五入しているため、合計が100%にならない場合がある
出典:J-FLEC「家計の金融行動に関する世論調査 2024年(二人以上世帯調査)」より筆者計算
金融資産の約半分が預貯金
上でまとめた表から分かる通り、金融資産の約半分が預貯金となっています。また、二人以上世帯の場合は単身世帯よりもディフェンシブになっているのか預貯金の割合はさらに高くなっています。このような状況では効率的にお金を増やしていくことはできません。
現在の金利状況下(普通預金金利:0.2%)では1000万円を普通預金に預けていても1年間で2万円しか利息が付きません。さらに、ここから税金として4063円引かれて実際に残る利息は15,937円です(分離課税の場合は復興特別所得税も合わせて20.315%の税金がかかります)。実際には全額普通預金というわけではなく40%程は定期預金なので、もう少し大きな額になりますが、老後により多くの資金を残したいのであれば預貯金から投資へと振り分ける額を増やした方がよいでしょう。
金融資産保有額が想像以上に多い?
余談にはなりますが、金融資産保有額が皆さんの実感よりも多くなっていると思います。これは、「金融資産保有世帯」の「平均」という二つの要素から高くなっています。同じ調査では金融資産を保有していない世帯は、単身世帯では32.8%、二人以上世帯では24.0%あります。これらの数字は含まれていません。また、平均値なので金融資産を多く待つ人がいたらその人に引っ張られて平均額は上昇します。特に、下限が0円と決まっているのでこの傾向は強く出ます。ゆえに、金融資産保有額が多く出ているのです。
預貯金が多いのは元本割れがないから?
同じく、J-FLEC「家計の金融行動に関する世論調査 2024年」からのデータですが、元本割れを起こす可能性があるが、収益性の高いと見込まれる金融商品の保有について、「そうした商品を保有しようとは全く思わない」と回答した人の割合は単身世帯で53.47%、二人以上世帯で47.6%と非常に多くなっています。
元本割れを嫌うがゆえに多くの資金が預貯金へと向かっているのだと考えられます。しかし、預貯金は元本割れしないというのは名目的には正しくても実質的には正しくありません。金利以上に物価が上昇したら預貯金は実質的には元本割れすることとなります。預貯金以外へも資産を振り分けていくことが大切でしょう。
預貯金以外の元本割れしにくい商品
投資が大切とはいってもいきなり株式や投資信託を購入するのはハードルが高いと感じる人が多いでしょう。そこで、投資へのハードルを低くするために元本割れしにくい商品を紹介します。これを取っ掛かりとしてより投資性の強い商品へと目を向けていくとよいでしょう。
積立保険
積立保険は早期解約すると元本割れするものが多いですが、一定期間以上契約し続けると返戻率(払い込んだ保険料総額に対する解約や満期で戻ってくる金額の割合)が100%を超える商品が多くあります。「保険による保障と貯蓄は分けて考えるべき」、「契約時に金利が固定されるからインフレに弱い」といった批判もありますが、一定期間継続して保険料を払い続けるという経験や払った保険料以上の金額が返ってくる、将来得られる金額を予測しやすいという面を考えると、初心者の第一歩としては十分候補の一つに挙げられると思います。
個人向け国債
個人向け国債は1万円から購入でき、元本割れしないので投資へのハードルが低く、金融商品を購入したという経験を得ることができます。個人向け国債の金利は0.05%が最低保証されているので、現在の金利状況下だと銀行の定期預金よりも高い金利を得ることができます。また、変動金利の10年満期のものを購入すれば、途中で金利が上昇したとしてもある程度対応することができます。1年経過後は直近2回分の利子相当額が差し引かれますが、中途換金も可能です。
まとめ
「貯蓄から投資へ」のスローガンが掲げられていますが、世帯が保有する金融資産の約半分は預貯金です。現在の低金利状況下で資産を効率的に増やしていくには投資へも資産を回していく必要があります。しかし、いきなり株式や投資信託を購入するのはハードルが高いと感じるのであれば、まずは積立保険や個人向け国債など元本割れのリスクが少ない商品で金融商品を購入するという経験をしましょう。

-
著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。