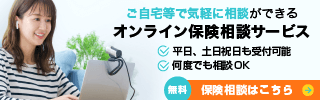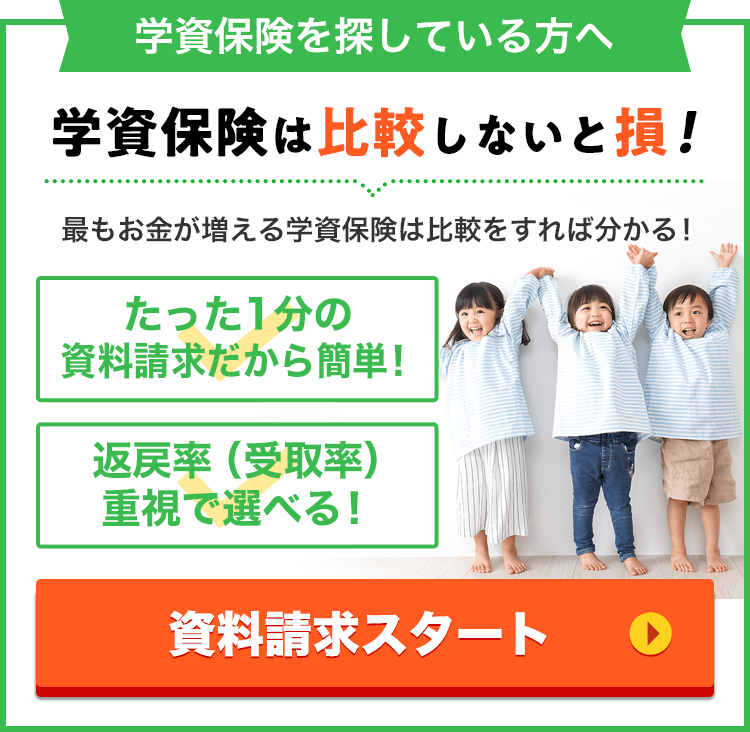学資保険は子供の教育資金をためるために昔から多くの人が加入してきました。しかし、「学資保険はメリットが薄く入る必要はない」という声を聞くこともあります。学資保険は必要なのかメリットとデメリットを整理します。
目次
学資保険のメリット
学資保険には以下のようなメリットがあります。
- 計画的に貯蓄ができる
- 契約者である親に万が一のことがあったら後の保険料が不要に
- 生命保険料控除で税金が安くなる
以下、順に説明していきます。
計画的に貯蓄できる
「毎月○円貯金しよう!」と貯金を始めてみても、続かなかったり貯金を取り崩してしまったりして失敗した経験がある方もいるのではないでしょうか。学資保険の場合、指定した口座から決められた日付に保険料という形で自動的に引き落とされます。また、引き落とされたお金は自分の自由にはできず、解約というひと手間が必要となります。そして、解約すると基本的に支払った保険料よりも少なくなるので解約には心理的な抵抗感があります。貯金が苦手な人でも計画的に貯蓄ができることが学資保険の一つのメリットといえます。
契約者である親に万が一のことがあったら後の保険料が不要に
多くの学資保険では契約者である親が死亡してしまったり所定の高度障害状態になってしまったりした場合に、のちの保険料の払い込みが免除されます。そして、将来支払われる予定の祝い金や満期保険金も予定通りもらうことができます。万が一のことがあって収入が途絶えても子供の教育資金にある程度の目途を立てることができるという点にメリットを感じる人も多いようです。
生命保険料控除で税負担を軽減
学資保険は生命保険料控除の対象なので、所得税に関しては最大で4万円、住民税に関しては最大で2万8千円の控除が受けられます(年間払込保険料が8万円超の場合)。例えば、年間払込保険料が8万円超で所得税率が10%(課税所得が195万円超330万円以下)、住民税率が10%の場合、年間で所得税が4,000円、住民税が2,800円、合計で6,800円安くなります。これが、保険料の払い込みが終わるまで続きます。ただし、他の生命保険で枠を使ってしまっているのならこの部分のメリットはなくなります。
| 所得税 | 住民税 | ||
|---|---|---|---|
| 年間の支払保険料等 | 控除額 | 年間の支払保険料等 | 控除額 |
| 20,000円以下 | 支払保険料等の全額 | 12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 | 12,000円超 32,000円以下 | 支払保険料等×1/2+6,000円 |
| 40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 | 32,000円超 56,000円以下 | 支払保険料等×1/4+14,000円 |
| 80,000円超 | 一律40,000円 | 56,000円超 | 一律28,000円 |
教育費の準備を「保険」で始める
学資保険のデメリット
学資保険には以下のようなデメリットもあります。
- 長期間資金が拘束される
- インフレに弱い
- 低金利時に契約するとあまり増えない
- 保険会社が破たんしたら全額の保護はされない
以下、デメリットについて説明します。
長期間資金が拘束される
学資保険は支払った保険料について学資保険を解約するか満期を迎えるまで動かすことができません。また、途中解約した場合に返ってくる解約返戻金は支払保険料よりも少なくなることがほとんどです。学資保険は18年など長期間の契約になるので長い間資金を動かしにくい状態が続くこととなります。
18年という長い期間では病気や事故などで急に大きな出費が必要になったり収入が減ったりする可能性も否定できませんので、緊急時の備えも別途用意できるとよいでしょう。
インフレに弱い
学資保険は基本的に契約時に受取時の金額も決まるので、契約してから保険金を受け取るまでの間にインフレで物価が上昇したら実質的に受け取れる額が減少することとなります。契約時の物価では200万円で足りるはずだったのに、受取時には240万円必要となっていた(18年間毎年1%の物価上昇)ということも考えられますが、学資保険で受け取れる金額は変わりません。
日本は長い間物価上昇率がマイナスか高くても+1%代という年が続きましたが、ここ最近は+2%を超える物価上昇が起きています。東京大学の授業料が値上げされたように大学で必要となるお金も増える可能性もあります。学資保険だけでなく家計に余裕があればNISAを利用して投資との併用を考えてみてもよいでしょう。
あまり大きくは増えない
学資保険は保険料を最後まで払い込めば決められた学資金・満期保険金を受け取れるので、株式投資等と比べてリスクは小さいですが、その分大きく増やすことは難しいです。例えば返戻率が105%の商品で200万円を受け取るには保険料で約190万円支払う必要があります。契約者死亡時の払い込み免除などもありますが、契約期間に対して増える金額だけに着目すると少し物足りなく感じるかもしれません。
保険会社が破たんしたら全額の保護はされない
学資保険を販売する保険会社は民間の事業者なので、当然のことながら破たんする可能性はゼロではありません。保険会社が破たんした場合、生命保険契約者保護機構によって責任準備金の9割は保護を受けることができます。言い換えれば残りの10%については保護されず無くなってしまう可能性があります。また、破たんした保険会社から契約を引き継いだ保険会社は予定利率を引き下げることができるので、受け取ることができる保険金も下がる可能性があります。
学資保険は必要?
メリットとデメリットをそれぞれ見てきましたが、結局のところ学資保険は必要なのでしょうか。その答えとしては、お金を貯めるのが苦手な人にとって有力な教育資金をためる方法の一つになる、というところだと思います。また、教育資金は必要となるタイミングが決まっているので、株式投資等を積極的に行う人であっても大学入学時などで最低限確保できる金額という意味合いを持たせることもできます。ただし、メリットばかりではなくデメリットもあるので、他の方法で教育資金をためることができるのなら学資保険に固執する必要はありません。
貯金が苦手、だけど子供の将来のためにお金をしっかり用意していきたいという人はまずは学資保険の資料請求から始めてみてはいかがでしょうか。インズウェブの学資保険一括資料請求サービスでは複数の保険会社の学資保険について一度に資料請求することができます。ぜひご利用してみてください。

-
著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。